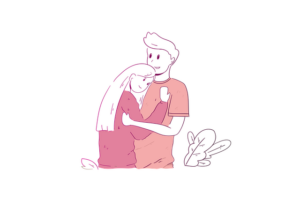結婚式費用を夫婦で平等に分担するためのルール作りと考え方
結婚式は、二人の人生の新たな門出を祝福する大切なイベントです。
しかし、その準備を進める中で、避けては通れないのが「費用」の問題。
特に、新郎新婦それぞれのご両親からの援助がある場合や、共働きで収入に差がある場合など、どのように費用を分担するかは、二人の関係性や将来にも影響を与えかねないデリケートなテーマです。
せっかくのお祝いの場が、お金のことでギスギスしてしまっては元も子もありません。
この記事では、結婚式費用を夫婦で「平等に」分担するための具体的なルール作りと、その根底にある考え方について、経験に基づいたアドバイスを交えながら詳しく解説していきます。
二人が納得できる形で、笑顔で結婚式を迎えるための一助となれば幸いです。
結婚式費用分担の基本:お互いの収入や貯蓄額を正直に共有すること
結婚式費用を平等に分担するためには、まず大前提として、お互いの収入や貯蓄額、そして結婚式にかけられる予算について、包み隠さず正直に共有することが不可欠です。
これは、単に「いくら持っているか」という数字の共有に留まらず、「毎月どのくらい貯蓄に回せるか」「将来的にどのくらいの金額が必要になるか」といった、将来設計も含めた話し合いが重要になります。
例えば、彼が貯蓄は多いものの、毎月の収入から自由に使えるお金が少ない場合と、彼女が毎月の収入は安定しているが、まとまった貯蓄はこれから、といったケースでは、分担の仕方も変わってきます。
具体的には、まずはお互いの現在の貯蓄額を把握し、そこから結婚式のために「いくらまでなら使っても良いか」という上限額を設定します。
次に、毎月の収入から、生活費や将来のための貯蓄などを差し引いた「毎月捻出できる結婚式費用」を計算します。
この「捻出できる額」を基に、結婚式全体の予算をどのように分担するかを話し合います。
例えば、新婦側のご両親からの援助が多めであれば、その分新郎側が負担する割合を減らす、といった調整も考えられます。
重要なのは、「どちらかが我慢する」のではなく、「二人で協力して、無理のない範囲で最高の結婚式を実現する」という共通認識を持つことです。
この初期段階でのオープンなコミュニケーションが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。
さらに、結婚式費用には、結婚指輪や新婚旅行、新居の初期費用など、結婚式そのもの以外にも関連する出費が多くあります。
これらの費用も、結婚式費用と合わせて「二人の門出にかかる費用」として、一緒に話し合い、分担を決めておくことをお勧めします。
例えば、結婚指輪は新郎が、新婚旅行は新婦が、といったように、それぞれの項目でどちらが負担するかを決めるのも一つの方法です。
あるいは、お互いの収入の割合に応じて、これらの関連費用も按分するという考え方もあります。
「結婚式」というイベントだけでなく、「結婚」という大きなライフイベント全体で費用を捉え、二人で協力して乗り越えていく姿勢が、円満な費用分担には不可欠なのです。
結婚式費用の具体的な分担方法:折半だけじゃない!多様な選択肢を知る
結婚式費用を分担する方法は、単純な「折半」だけではありません。
お互いの収入や価値観、ご両親からの援助の有無など、様々な要因を考慮して、より現実的で納得のいく方法を選択することが大切です。
ここでは、いくつかの具体的な分担方法と、それぞれのメリット・デメリット、そして独自の視点からのアドバイスをご紹介します。
収入割合に応じた分担:公平性を重視するなら
最も公平性が高いとされるのが、お互いの収入割合に応じて費用を分担する方法です。
例えば、新郎の年収が500万円、新婦が300万円であれば、収入の合計が800万円のうち、新郎が5/8、新婦が3/8の割合で負担するという考え方です。
この方法の最大のメリットは、収入の差による不公平感が生じにくい点です。
お互いが無理なく負担できる範囲で、結婚式という一大イベントを迎えられます。
しかし、この方法を実践する上で、「収入」の定義を明確にしておくことが重要です。
手取り額なのか、額面なのか、あるいはボーナスを含めるのかなど、事前にしっかりと話し合い、合意を得ておく必要があります。
また、収入は変動するものですから、結婚式直前の収入で計算するのか、それとも平均収入で計算するのかといった点も考慮が必要です。
さらに、この方法を採用する場合、お互いの収入をオープンに共有する必要があります。
これは、お互いの経済状況への理解を深める良い機会となりますが、デリケートな話題でもあるため、信頼関係が十分に築けていることが前提となります。
もし、収入をオープンにすることに抵抗がある場合は、この方法以外の選択肢を検討する必要があるでしょう。
私たちが実際に経験したカップルの中には、この収入割合分担を取り入れたものの、計算が複雑になることを避けるため、「収入の差額分だけ、どちらかが多く負担する」という簡易的な方法を採用したケースもありました。
例えば、収入の高い方が、差額の半分を余分に負担するという形です。
このように、計算のしやすさや、お互いの手間も考慮して、柔軟にアレンジすることも可能です。
大切なのは、二人にとって最も納得感があり、かつ継続可能な方法を見つけることです。
ご両親からの援助を考慮した分担:感謝の気持ちを形に
ご両親からの援助がある場合、その援助額を考慮して費用を分担する方法も一般的です。
例えば、ご両親から新婦側へまとまった援助があった場合、その分新婦の負担額を減らし、新郎の負担額を増やす、といった調整です。
この方法のポイントは、援助に対する感謝の気持ちを忘れずに、それを費用分担に反映させることです。
しかし、ここで注意したいのは、援助の意図をしっかりと確認することです。
ご両親からの援助は、必ずしも「新婦側への援助」とは限りません。
「二人の結婚式を応援したい」という気持ちからの援助である場合も多く、その場合、援助額を一方の負担減に充てるのではなく、結婚式全体の費用から差し引いて、二人で新たに分担額を計算し直すという考え方もあります。
例えば、ご両親から「結婚式のために○万円援助したい」という申し出があった場合、その○万円を結婚式総予算から引いた残りの費用を、二人で折半する、あるいは収入割合で分担するといった形です。
また、援助の受け取り方についても、事前に話し合っておくことが重要です。
援助されたお金を、そのまま結婚式費用として使うのか、あるいは新婚旅行の資金に充てるのかなど、援助の使途についても二人で合意しておきましょう。
「ご両親の温かい気持ちを、どのように形にしていくか」という視点で話し合うと、より建設的な結論に至りやすいはずです。
私たちの知人カップルは、ご両親からの援助を、結婚式当日だけでなく、新生活を始めるための家具家電購入資金に充てるという選択をしていました。
このように、結婚式というイベントだけでなく、その先の二人の生活全体を見据えた費用分担を考えることも、感謝の気持ちを伝える一つの方法と言えるでしょう。
「新婦側」「新郎側」の慣習にとらわれない分担:新しい時代の結婚式
かつては、「結婚式費用は新郎側が多めに負担する」「結婚指輪は新郎が贈る」といった、いわゆる「慣習」がありましたが、現代ではそのような慣習にとらわれず、二人にとって最も合理的な方法で費用を分担するカップルが増えています。
例えば、結婚式にかかる費用のうち、会場装飾や衣装、引出物など、どちらかといえば新婦側がこだわりたい部分の費用は新婦が、演出や映像関係など、どちらかといえば新郎側がこだわりたい部分の費用は新郎が、といったように、それぞれのこだわりや得意分野に応じて負担するという考え方です。
この方法の魅力は、お互いの「やりたいこと」を尊重しながら、費用を分担できる点にあります。
例えば、新婦がどうしても着たいドレスがあり、それが予算オーバーになりそうな場合でも、新郎が担当する部分の費用を抑えることで、新婦の希望を叶えることができるかもしれません。
逆に、新郎がこだわりの映像演出をしたい場合、新婦が衣装代を少し抑えることで、新郎の希望を叶えることも可能です。
「どちらかの希望を優先する」のではなく、「お互いの希望を叶えるために、どう分担するか」という視点が重要になります。
この分担方法を成功させるためには、何にこだわりたいか、何を重視したいか、といったお互いの価値観をしっかりと共有することが不可欠です。
漠然と「新郎側」「新婦側」と分けるのではなく、具体的な項目ごとに「これはどちらが担当するか」「どちらが費用を出すか」をリストアップし、話し合っていくのが効果的です。
また、この方法を採用する場合、「どちらがどれだけ負担したか」という細かい金額の精算よりも、「お互いの希望を叶えられたか」という満足度を重視することが、円満な関係を築く上で大切になります。
時には、お互いの負担額に多少の差が出たとしても、それをお互いが納得できるのであれば、問題ないのです。
結婚式費用分担のルール作りのポイント:後悔しないための注意点
結婚式費用を夫婦で平等に分担するためのルール作りは、単に金額を分けるだけではありません。
将来にわたって良好な関係を築き、後悔のない結婚式を迎えるために、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、具体的なルール作りの進め方と、注意すべき点について解説します。
「両家」と「二人」のバランスを考える:両親への配慮も忘れずに
結婚式は、二人の門出であると同時に、両家が結びつく大切なイベントでもあります。
そのため、費用分担を考える際には、新郎新婦の二人だけでなく、両親の意向や、両家間のバランスも考慮に入れることが大切です。
例えば、新婦側のご両親が「自分たちの結婚式だから、二人の貯蓄から出すべき」と考えている場合、無理に援助を求めるのではなく、その意向を尊重することも必要です。
逆に、新郎側のご両親が「結婚式は親の役目」と考えて、多額の援助を申し出てくれる場合でも、援助を無条件に受け入れるのではなく、その金額や使途について、新郎新婦の二人でしっかりと話し合い、意思表示をすることが重要です。
例えば、「ありがたいお話ですが、結婚式は自分たちで計画したいので、その分は新生活の資金に充てさせてください」といった、丁寧なコミュニケーションが求められます。
「両家への感謝の気持ち」と「自分たちの結婚式」という、二つのバランスをどう取るかが、円満な関係を築く上で鍵となります。
私たちが実際に相談を受けたカップルの中には、両家顔合わせの際に、結婚式の費用分担について、両親も交えて話し合ったというケースがありました。
この場合、事前に新郎新婦の間で、ある程度の方向性を決めておくことが重要です。
両親の意見を聞きながら、最終的な決定は二人で行う、というスタンスを崩さないようにしましょう。
このように、「両親への敬意」と「自分たちの意思決定」のバランスをうまくとることで、両家ともが気持ちよく結婚式を迎えることができるでしょう。
「見えない費用」にも目を向ける:後から発覚する出費に注意
結婚式費用と聞くと、会場費や衣装代、料理代などが真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、実際には「見えない費用」がたくさん存在します。
例えば、結婚式の準備を進める中で発生する交通費、打ち合わせのためのランチ代、式場とのやり取りで必要になる通信費、そして何よりも、結婚式準備期間中のストレス発散のための食事代や、お互いを労うためのプレゼント代なども、広義には結婚式に関わる費用と言えるかもしれません。
これらの「見えない費用」は、時に積み重なると無視できない金額になることもあります。
そのため、費用の分担ルールを決める際には、これらの「見えない費用」についても、どのように扱うか話し合っておくことをお勧めします。
例えば、「二人で共通の貯金口座を作り、そこから結婚式関連の雑費を支払う」「お互いの交通費は各自で負担する」など、具体的な取り決めをしておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
「細かいことまで決めすぎると、かえって窮屈になるのでは?」と思うかもしれませんが、ある程度のルールを決めておくことで、かえって精神的な負担が軽くなることもあります。
また、結婚式当日に発生する「ご祝儀」についても、事前にどう扱うかを決めておくことが大切です。
例えば、ご祝儀を新郎側と新婦側で分けて精算するのか、それとも全てを「二人のもの」として、新生活の資金に充てるのかなど、ご祝儀の扱いについても、二人で話し合っておくことで、後々の疑問や不満を解消することができます。
「自分たちの結婚式」という意識を