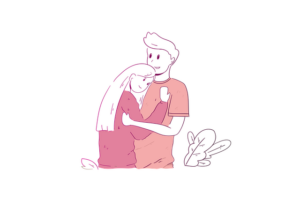結婚式の持ち込み料を賢く節約!知っておきたい交渉術と節約術を徹底解説
結婚式は人生の大きな節目であり、多くのカップルにとって夢の舞台です。
しかし、その華やかさの裏側には、想像以上の費用がかかることも少なくありません。
特に、結婚式場によっては、外部から持ち込んだアイテムに対して「持ち込み料」が発生することがあります。
この持ち込み料、実は上手に節約したり、場合によっては交渉して無料にすることも可能なのです。
この記事では、結婚式の持ち込み料を賢く節約するための具体的な方法と、式場との交渉で役立つポイントを、経験豊富なウェディングプランナーの視点から徹底的に解説します。
あなたらしい理想の結婚式を実現するために、ぜひこの記事を参考に、賢く費用を抑えましょう。
結婚式場との賢い付き合い方:持ち込み料を理解し、節約の糸口を見つける
結婚式の準備を進める中で、多くのカップルが直面する「持ち込み料」。
この言葉を聞くと、どうしてもネガティブなイメージを抱きがちですが、実は式場側にも様々な事情があります。
持ち込み料が発生する背景を理解し、それを踏まえた上で、式場と良好な関係を築きながら節約の道を探ることが大切です。
持ち込み料が発生する理由と、式場側の本音を理解する
結婚式場が持ち込み料を設定するのには、いくつかの理由があります。
まず、式場側は、自社で仕入れた商品やサービスを提供することで、一定の利益を確保しています。
外部からの持ち込みは、その利益を圧迫する可能性があります。
また、持ち込み品によっては、式場の設備を汚損したり、提供する料理や飲み物の品質に影響を与えたりするリスクも考慮されます。
さらに、式場側としては、提携している外部業者との関係性や、自社のブランドイメージを維持するためにも、一定のルールを設ける必要があるのです。
しかし、これは必ずしも「持ち込み=悪」というわけではありません。
式場側も、新郎新婦のこだわりを尊重したいと考えている場合も多く、柔軟に対応してくれるケースも少なくありません。
例えば、どうしても譲れないアイテムがある場合や、費用を抑えたいという明確な理由がある場合、それを丁寧に伝えることで、持ち込み料の免除や割引に応じてくれる可能性も十分にあります。
重要なのは、一方的に「持ち込みたい」と主張するのではなく、式場の立場を理解し、 mutual benefit(相互利益)の精神で話し合うことです。
例えば、「このアイテムは、どうしてもこのデザイナーさんのものを使いたいのです。
もし可能であれば、持ち込み料についてご相談させていただけないでしょうか?」といったように、具体的な理由と丁寧な言葉遣いを心がけることで、式場側の理解を得やすくなります。
持ち込み料の交渉が成功しやすいアイテムと、その交渉術
全てのアイテムで持ち込み料の交渉が成功しやすいわけではありませんが、一般的に交渉がしやすいとされるアイテムがいくつか存在します。
これらを把握しておくだけでも、節約の可能性が大きく広がります。
まず、ペーパーアイテム(招待状、席次表、席札など)は、比較的持ち込みが認められやすいアイテムの一つです。
これらは、式場の収益に直接大きく関わるものではない場合が多く、デザインにこだわりたいという新郎新婦の要望にも応えやすいためです。
交渉する際は、「インターネットで素敵なデザインを見つけたのですが、こちらを持ち込ませていただくことは可能でしょうか?」「もし可能であれば、持ち込み料についてお伺いできますでしょうか?」と、あくまで相談ベースで切り出すのが良いでしょう。
次に、ウェルカムボードやリングピロー、プチギフトなども、持ち込みが比較的スムーズに進みやすいアイテムです。
これらは、新郎新婦の趣味や手作り感を活かしたいという気持ちが表れやすいアイテムであり、式場側もそれを理解してくれる傾向があります。
交渉の際は、「二人の思い出の品をウェルカムボードにしたいと考えているのですが、持ち込みは可能でしょうか?」といったように、アイテムに込められた意味合いを伝えることで、より共感を得やすくなります。
さらに、引き出物や引き菓子についても、交渉の余地がある場合があります。
ただし、これらは式場の料理やドリンクのコース内容と連動していることも多いため、式場側としては慎重になる傾向があります。
もし持ち込みを希望する場合は、「こちらの引き出物は、ゲストの方々に喜んでいただけるものを選びたいと考えております。
もしよろしければ、持ち込み料についてご相談させていただけますでしょうか?」と、ゲストへの配慮を前面に出して相談すると良いでしょう。
交渉の際の秘訣は、早めに式場とコミュニケーションを取ることです。
契約前に持ち込みに関する規約を確認し、希望するアイテムがあれば、その時点で担当者に相談しましょう。
契約後になってから「やっぱりこれ持ち込みたいんだけど…」と伝えるよりも、事前に相談しておく方が、式場側も代替案を考えたり、柔軟に対応しやすくなります。
また、「他の式場では持ち込み料がかからなかった」といった比較論で交渉するのは避けましょう。
あくまで、その式場で実現したい結婚式のために、相談をしているという姿勢が大切です。
賢く節約!持ち込み料を回避・軽減するための具体的な戦略
持ち込み料の交渉が難しい場合や、そもそも持ち込み料を発生させないための戦略も存在します。
ここでは、より実践的で具体的な節約方法を、独自の視点も交えてご紹介します。
式場との初期契約を最大限に活用する:持ち込み料免除の交渉術
結婚式の契約は、まさにこれから始まる結婚式という物語の「序章」であり、ここでいかに賢く立ち回るかが、その後の費用に大きく影響します。
特に、持ち込み料に関しては、契約前にしっかりと交渉し、免除や割引の約束を取り付けることが、最も効果的な節約術と言えるでしょう。
多くの式場では、契約時に「初期成約特典」や「早期割引」といった形で、様々なサービスを提供しています。
この特典の中に、「持ち込み料全額免除」や「一部アイテムの持ち込み料無料」といった項目が含まれている場合があります。
もし、契約を急いでいる状況でないのであれば、複数の式場を比較検討する中で、持ち込み料に関する条件を最重要視して選びましょう。
また、契約時に「このアイテムだけは、どうしても外部から持ち込みたい」という強い希望がある場合は、それを担当者に率直に伝え、「もし、このアイテムの持ち込み料を免除していただけるなら、他のアイテムは式場のものを使わせていただきます」といったように、代替案を提示するのも有効な交渉術です。
式場側も、全ての持ち込みを断るのではなく、一部のアイテムに限り柔軟に対応することで、新郎新婦の満足度を高め、最終的な契約に繋げたいと考えています。
さらに、「持ち込み料がかかるなら、その分、他の項目で割引してもらえませんか?」と、持ち込み料の代わりに、料理や装花、衣装などの割引を交渉するのも一つの手です。
式場側も、トータルの費用を抑えたいという新郎新婦の意向を理解していれば、柔軟に対応してくれる可能性があります。
重要なのは、あくまで「相談」というスタンスを崩さないこと。
「これができないなら契約しません」というような高圧的な態度は、かえって交渉を難しくしてしまいます。
賢い外部業者の活用と、式場との連携をスムーズにするコツ
持ち込み料を回避する最も直接的な方法は、外部の業者に依頼することですが、ここでも注意点があります。
安易に外部業者に依頼してしまうと、思わぬトラブルや、式場との連携不足から、かえって費用がかさんでしまうことも。
外部業者を活用する際は、式場との連携を最優先に考えましょう。
例えば、カメラマンやビデオグラファーは、外部に依頼することで、式場提携の業者よりもリーズナブルな価格で、より自分たちのイメージに合った写真や映像を残せる可能性があります。
しかし、外部のカメラマンを依頼する場合、式場によっては「持ち込み料」を設定している場合があるため、事前に必ず確認が必要です。
また、式場側は、外部のカメラマンに対して、撮影場所の制限や、機材の持ち込みに関するルールを設けていることもあります。
交渉の際は、「式場のルールを遵守し、他のゲストのご迷惑にならないように撮影いたします」と、式場側の懸念を払拭するような説明を添えると良いでしょう。
ヘアメイクや、ブーケ、引き出物なども、外部で手配することで節約できる場合があります。
しかし、式場によっては、外部のヘアメイクアーティストの利用を制限していたり、外部のブーケを持ち込む際に、会場装花との兼ね合いで制限を設けたりすることもあります。
外部業者を選ぶ際は、必ず式場に事前に相談し、許可を得てから契約を進めましょう。
その際、「式場の担当者様とも事前に打ち合わせをさせていただきますので、ご安心ください」と伝えることで、式場側も安心感を得やすくなります。
さらに、式場提携の外部業者リストがある場合、そのリストの中から選ぶことで、持ち込み料が免除されるケースも少なくありません。
リストアップされている業者は、式場側も信頼しており、連携もスムーズに進むため、トラブルのリスクを減らすことができます。
「もし、リストの中から選ぶ場合、どのような特典がありますか?」と質問してみるのも良いでしょう。
一次情報として、筆者の経験談を交えてお伝えすると、以前担当したカップルで、ご友人がプロのイラストレーターだったため、オリジナルのウェルカムボードを制作してもらったケースがありました。
その際、式場側は当初持ち込み料を提示されましたが、「このウェルカムボードは、新郎新婦の共通の趣味である〇〇をモチーフにしており、二人の思い出を形にした特別なものです。
もし、持ち込み料がかかるのであれば、式場側で用意していただくものにしたいのですが、二人のこだわりを叶えたいという気持ちが強く、ご相談させていただきました」と丁寧に伝えたところ、式場側が、「お二人の熱意に感銘を受けました。
今回は特別に、持ち込み料はいただきませんが、もし万が一、制作中に問題が発生した場合は、速やかに式場にご報告ください」と、持ち込み料を免除してくれたのです。
このように、アイテムに込められたストーリーや、新郎新婦の強いこだわりを伝えることは、式場側の心を動かす強力な武器になり得ます。
まとめ
結婚式の持ち込み料は、賢く付き合うことで、賢く節約できるポイントがたくさんあります。
式場側の事情を理解し、丁寧なコミュニケーションを心がけること、そして、交渉が成功しやすいアイテムや、具体的な節約戦略を把握しておくことが重要です。
初期契約の段階で持ち込み料の免除や割引を交渉したり、外部業者を上手に活用したりすることで、理想の結婚式費用を抑えることは十分に可能です。
この記事でご紹介した情報を参考に、あなたらしい最高の結婚式を実現させてください。