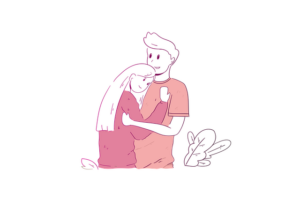結婚は人生における素晴らしい節目ですが、同時にかかる費用について漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
プロポーズから始まり、婚約、結婚式、新婚旅行、そして新しい生活のスタートまで、様々なイベントが続きます。
それぞれに費用が発生するため、「結婚までにかかる費用総額は一体いくらになるのか?」「その内訳はどうなっているの?」といった疑問を持つのは自然なことです。
この記事では、結婚にかかる費用について、具体的な総額の目安から詳細な内訳、さらには賢く費用を抑えるための節約術まで、網羅的に解説していきます。
ぜひ、お二人の結婚準備の参考にしてください。
結婚までにかかる費用、総額はいくら?全体像を知ろう
結婚を具体的に考え始めると、まず気になるのが「一体いくらあれば結婚できるのだろう?」という費用総額の疑問ですよね。
この総額には、プロポーズや婚約指輪、結婚指輪といった婚約段階の費用、両家顔合わせや結納の費用、そして最も大きな割合を占めることが多い結婚式・披露宴の費用、さらに新婚旅行や新居への引っ越し、家具家電の購入といった新生活のスタートにかかる初期費用などが含まれます。
これらの費用を全て合算したものが、結婚までにかかる費用総額となります。
ただし、この総額は、お二人の価値観やどのような結婚スタイルを選ぶかによって大きく変動します。
例えば、盛大な結婚式を挙げるのか、家族だけで行うのか、あるいは入籍だけにするのかによって、必要な金額は全く変わってきます。
また、新婚旅行の行き先や期間、新居の家賃や購入する家具家電のグレードなど、様々な要素が影響します。
大切なのは、平均値を知るだけでなく、お二人にとって何が重要かを話し合い、それに合った費用計画を立てることです。
漠然とした不安を解消するためにも、まずは全体像を把握し、具体的な内訳を見ていくことが第一歩となります。
先輩カップルの平均費用データをチェック
結婚にかかる費用総額の目安を知る上で参考になるのが、ゼクシィなどのブライダル情報誌が毎年行っているアンケート調査です。
この調査によると、挙式、披露宴・ウェディングパーティーにかかった費用の全国平均は、約300万円台後半から400万円台前半で推移しています。
これに婚約指輪や結婚指輪、新婚旅行、結納・顔合わせ、二次会などの費用を加えると、結婚に関連する一連の費用総額は、平均で500万円を超えることも珍しくありません。
ただし、これはあくまで「平均」であり、中央値はもう少し低いこともありますし、地域によっても差があります。
例えば、都市部の方が地方よりも平均費用が高くなる傾向が見られます。
また、この平均値には、ゲストからのご祝儀や両親からの援助が含まれていない「自己負担額」の平均と、ご祝儀や援助を含めた「総支払額」の平均があるため、どちらの数字を見ているのか確認することも重要です。
多くのカップルが、ご祝儀や援助を差し引いた自己負担額を100万円台後半から200万円台で考えているようです。
この平均データは、あくまで自分たちの予算を考える上での「参考」として捉えましょう。
自分たちの理想や状況に合わせて、必要な項目と不要な項目を検討し、現実的な予算を立てることが何よりも大切です。
総額が高くなる要因と安くなる要因
結婚にかかる費用総額が平均よりも高くなる、あるいは安くなるのは、どのような要因によるのでしょうか。
総額が高くなる主な要因としては、まず結婚式の規模や内容が挙げられます。
招待するゲストの人数が多ければ多いほど、料理や引出物の費用がかさみます。
また、選ぶ式場のグレード、料理やドリンクのランクアップ、衣装のこだわり(お色直し回数やブランドなど)、装花や演出の追加、写真や映像のプロへの依頼なども費用を押し上げる要因となります。
さらに、婚約指輪や結婚指輪に高価なブランドを選んだり、カラット数の大きいダイヤモンドを選んだりする場合も費用は高くなります。
新婚旅行も、行き先が遠方であったり、滞在日数が長かったり、宿泊施設やアクティビティを豪華にしたりすると費用がかさみます。
一方、総額を安く抑える要因としては、結婚式のスタイルを工夫することが最も効果的です。
例えば、盛大な披露宴ではなく、親族のみでの挙式・食事会にする、リゾートウェディングや海外ウェディングを選ぶ(旅費はかかるが、式自体は比較的安価な場合も)、あるいは入籍のみにするといった選択肢があります。
また、手作りのアイテムを取り入れたり、衣装をレンタルではなく購入して二次会などでも活用したり、写真や映像はプロではなく友人に頼むといった工夫も節約につながります。
新婚旅行に行かない、あるいは近場にする、婚約指輪なしで結婚指輪のみにする、家具家電は中古品やアウトレットを活用するなど、様々な方法で費用を抑えることが可能です。
結婚費用の具体的な内訳を徹底解説!項目別に見てみよう
結婚までにかかる費用総額を把握するためには、その具体的な内訳を知ることが不可欠です。
結婚に関わる費用は多岐にわたりますが、大きく分けて「婚約段階」「結婚式・披露宴」「新婚旅行」「新生活準備」の4つのカテゴリーに分類できます。
それぞれのカテゴリー内で、どのような項目にどれくらいの費用がかかるのかを詳しく見ていきましょう。
内訳を細かく把握することで、どこに費用をかけるべきか、どこで費用を抑えられるのかが見えてきます。
漠然と「高い」と感じるだけでなく、具体的な項目ごとに金額感を掴むことが、賢い費用計画を立てるための第一歩です。
また、それぞれの項目にかかる費用は、地域や時期、そしてお二人のこだわりによって大きく変動することを理解しておくことも重要です。
例えば、結婚式の費用は、同じ規模でも選ぶ式場や日取り(トップシーズンかオフシーズンか)によって全く異なります。
新婚旅行も、国内か海外か、アジアかヨーロッパか、滞在日数などによって費用は大きく変わってきます。
プロポーズ・婚約段階にかかる費用
結婚の始まりとも言えるプロポーズの段階から費用は発生します。
まず代表的なのが、婚約指輪の費用です。
婚約指輪の相場は給料の3ヶ月分と言われた時代もありましたが、最近の調査では平均で30万円~40万円程度が最も多い価格帯となっています。
もちろん、ブランドやダイヤモンドの大きさ、品質によって価格は大きく変動するため、10万円台で購入する方もいれば、100万円以上かける方もいらっしゃいます。
大切なのは相場にとらわれすぎず、贈る相手に喜んでもらえるもの、そして予算とのバランスを考えて選ぶことです。
また、プロポーズの際に、特別な場所を用意したり、サプライズ演出を企画したりする場合、その場所代や演出にかかる費用が発生することもあります。
さらに、婚約が成立した後、両家が集まって挨拶や親睦を深める「両家顔合わせ」や、正式に婚約を調える「結納」を行う場合も費用がかかります。
顔合わせは食事会形式が一般的で、会場となる料亭やレストランでの飲食代が主な費用となります。
参加人数にもよりますが、数万円から10万円程度が目安となることが多いです。
結納は、結納品や結納金、結納を執り行う場所の費用などがかかり、顔合わせよりも費用が高くなる傾向があります。
最近では結納を簡略化したり、顔合わせのみで済ませたりするカップルも増えています。
結婚式・披露宴にかかる費用とその仕組み
結婚式・披露宴は、結婚にかかる費用の中で最も大きな割合を占めることが一般的です。
前述の通り、全国平均では300万円台後半から400万円台前半が目安となりますが、これはあくまで平均であり、内容によって大きく変動します。
結婚式・披露宴にかかる費用は、主に「会場使用料」「料理・ドリンク」「衣装」「装花」「写真・映像」「演出」「引出物・引菓子」「ペーパーアイテム」などの項目に分けられます。
これらの費用は、ゲストの人数に応じて変動する項目(料理、ドリンク、引出物など)と、固定でかかる項目(会場使用料、プロへの依頼費など)があります。
例えば、料理は一人あたり1万円~2万円以上が一般的で、これにフリードリンク代が加わります。
引出物・引菓子も一人あたり5千円~1万円程度が見込まれます。
衣装は、新郎新婦の衣装レンタル代や着付け・ヘアメイク代がかかります。
装花は、会場装花やブーケなど、会場を華やかに飾るための費用です。
写真・映像は、プロのカメラマンやビデオグラファーに依頼する場合の費用です。
演出は、例えばキャンドルサービスやデザートビュッフェ、生演奏などを追加する場合にかかる費用です。
これらの費用は、選ぶアイテムのグレードや量、依頼する業者によって大きく変わります。
式場によっては、パッケージプランを用意している場合もありますが、自分たちのこだわりたい部分とそうでない部分を明確にし、一つ一つの項目を検討することが重要です。
また、結婚式費用は、契約時に見積もりが出ますが、打ち合わせを進める中で希望を追加したりグレードアップしたりすることで最終的な金額が見積もりから大きく跳ね上がることも少なくありません。
最初の見積もりは最低限の金額であることが多いため、実際にかかる費用は見積もりの1.2倍~1.5倍程度になる可能性も考慮しておきましょう。
結婚後の新生活にかかる初期費用と賢く抑える節約術
結婚はゴールではなく、新しい生活のスタートです。
そして、この新生活を始めるにあたっても、まとまった初期費用が必要になります。
特に、これから二人で一緒に住むための準備には、見落としがちな費用が多く含まれています。
これらの費用を事前に把握し、計画に含めておくことが、結婚後の家計をスムーズにスタートさせるために非常に重要です。
また、結婚にかかる費用全体を考える上で、結婚式だけでなく、この新生活の初期費用も含めてトータルで予算を考えることが大切です。
結婚式で費用をかけすぎたために、新生活のスタートが厳しくなってしまった、という事態は避けたいものです。
新生活にかかる主な初期費用としては、新居への引っ越し費用や契約にかかる費用、そして家具や家電の購入費用が挙げられます。
これらの費用は、住む場所やライフスタイルによって大きく変動するため、早めに情報収集を始め、具体的な金額感を掴むことが重要です。
新居・家具家電にかかる初期費用
新婚生活を始めるために新しい住居を探す場合、まずかかるのが新居の契約に関する初期費用です。
賃貸物件の場合、一般的に敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、日割り家賃、鍵の交換費用、火災保険料などが必要になります。
これらを合計すると、家賃の4ヶ月分から6ヶ月分程度が目安となることが多いです。
例えば、家賃10万円の物件であれば、初期費用として40万円から60万円程度が必要になる計算です。
敷金や礼金がかからない物件もありますが、その分家賃設定が高めであったり、退去時の費用が高額になったりする場合もあるため、総合的に判断する必要があります。
また、引っ越し業者に依頼する場合は、引っ越し費用もかかります。
時期や荷物の量、移動距離によって異なりますが、数万円から十数万円程度が見込まれます。
自分たちで運ぶなど工夫すれば費用は抑えられますが、手間と労力がかかります。
新居が決まったら、次に必要になるのが家具や家電の購入です。
冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、掃除機といった生活必需家電から、ベッド、ソファ、ダイニングテーブル、収納家具などの家具まで、一から揃えるとなるとかなりの金額になります。
全て新品で揃える場合、家電だけで数十万円、家具もこだわると数十万円以上かかることは珍しくありません。
どこまで既存のものを使うか、何を新しく購入するか、リストアップして優先順位をつけることが大切です。
結婚費用を抑えるための具体的な節約術
結婚にかかる費用は決して少なくありませんが、工夫次第で賢く費用を抑えることは十分に可能です。
特に、最も費用がかかることが多い結婚式・披露宴については、様々な節約術があります。
まず、日取りや時間帯を工夫することが挙げられます。
結婚式のトップシーズンである春や秋の土日祝日を避け、比較的費用が抑えられる夏や冬、あるいは平日の午後に挙式・披露宴を行うことで、会場費やプラン料金が割引になることがあります。
また、仏滅などの六曜を気にしないのであれば、さらに割引が適用される場合もあります。
次に、招待するゲストの人数を厳選することです。
ゲスト一人あたりにかかる費用は、料理や引出物、席次表などで数万円に上るため、人数を減らすことが直接的な節約につながります。
本当に大切な人たちだけを招待する、という考え方も良いでしょう。
さらに、手作りアイテムを取り入れることも有効です。
招待状や席次表、ウェルカムボードなどを自分たちで作成することで、印刷費や業者への依頼費を節約できます。
ただし、クオリティや手間とのバランスを考える必要があります。
衣装については、提携ショップ以外のドレスを持ち込むと持ち込み料がかかる場合があるため、提携ショップ内で気に入るものを見つけるか、持ち込み料がかからない式場を選ぶと良いでしょう。
また、レンタルではなく購入して、二次会や後撮りなどで再利用する方法もあります。
料理やドリンクは、ランクアップすると費用が跳ね上がるため、基本プランでも十分満足できる内容か確認し、どうしてもこだわりたい部分だけをランクアップする、という考え方も大切です。
引出物も、ゲストによって贈り分けをするなど、予算に合わせて調整しましょう。
結婚式以外では、婚約指輪を省略したり、結婚指輪を手頃な価格帯のブランドや素材を選んだりするのも節約になります。
新婚旅行も、行き先を近場にしたり、オフシーズンを選んだり、パッケージツアーではなく個人手配で工夫したりすることで費用を抑えられます。
新生活の家具家電も、全て新品で揃えるのではなく、実家から譲ってもらったり、フリマアプリやリサイクルショップを活用したり、レンタルサービスを利用したりすることで初期費用を抑えることができます。
結婚に関する補助金や祝い金制度がある自治体もあるため、お住まいの地域の情報を調べてみるのも良いでしょう。
そして何より大切なのは、お二人でしっかりと話し合い、何に費用をかけたいのか、どこを節約したいのか、価値観を共有することです。
まとめ
結婚までにかかる費用は、婚約から新生活のスタートまで多岐にわたり、その総額は平均で500万円を超えることもあります。
しかし、これはあくまで平均値であり、お二人の希望やライフスタイルによって大きく変動します。
プロポーズや婚約指輪、両家顔合わせや結納といった婚約段階の費用、結婚式・披露宴の費用、新婚旅行費用、そして新居への引っ越しや家具家電の購入といった新生活の初期費用など、様々な項目に費用が発生します。
特に結婚式・披露宴は全体の費用の中で大きな割合を占めることが一般的ですが、ゲスト数や式場のグレード、演出などによって金額は大きく変わります。
新生活の準備も、賃貸物件の初期費用や家具家電の購入など、まとまった金額が必要になる項目です。
これらの費用を全て含めて、結婚までにかかる費用総額として捉え、具体的な内訳を把握することが、賢い費用計画を立てるための第一歩となります。
費用を賢く抑えるためには、結婚式の日取りや時間帯、ゲスト数の調整、手作りアイテムの活用、衣装や引出物の選び方など、様々な節約術があります。
また、婚約指輪や新婚旅行、新生活の準備においても、工夫次第で費用を抑えることが可能です。
最も重要なのは、お二人でしっかりと話し合い、何に価値を置き、何に費用をかけたいのか、どこを節約できるのか、お互いの考えを共有することです。
漠然とした不安を抱えるのではなく、現実的な数字を把握し、お二人にとって最適な費用計画を立てることで、心穏やかに結婚準備を進めることができるでしょう。
結婚はお金が全てではありませんが、費用についてしっかり向き合うことは、お二人の将来設計を考える上で非常に大切なプロセスです。
この記事が、皆様の結婚準備の一助となれば幸いです。