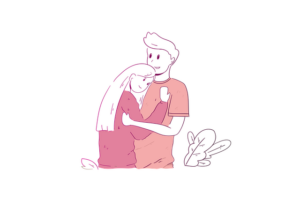結婚式場の下見、後悔しないための「測定・記録・冷静さ」3点セットとは?
結婚式場の下見は、一生に一度の晴れ舞台を彩る大切な場所を決める、わくわくするイベントですよね。
でも、初めてのことばかりで、何に注目すれば良いのか、どんなことを聞けば良いのか、迷ってしまうことも多いはず。
せっかくの下見で「あれも聞けばよかった」「これも確認しておけばよかった」と後悔しないためには、「測定・記録・冷静さ」の3点セットを準備して臨むことが何よりも大切です。
この3つがあれば、理想の結婚式場を効率よく見つけ出し、後々のトラブルを防ぎ、心から納得のいく結婚式を実現できるでしょう。
この記事では、結婚式場の下見を最大限に活用するための具体的な持ち物と、それぞれの重要性について、あなたの結婚準備を全力でサポートするべく、詳しく解説していきます。
会場の「サイズ感」を掴むための測定グッズ
結婚式場の広さや雰囲気は、写真やパンフレットだけではなかなか伝わりにくいものです。
実際に訪れて、五感で確かめることが不可欠ですが、その際に役立つのが「測定グッズ」です。
これらを活用することで、より具体的なイメージを掴み、後々のプランニングに役立てることができます。
メジャーで会場の「リアルな広さ」を把握する
まず、必須とも言えるのがメジャーです。
会場の広さを数値で把握することは、装飾やゲストの配置、演出などを具体的にイメージする上で非常に重要です。
「このテーブル配置で何名くらい座れるかな?」「このスペースにあの演出はできるかな?」といった疑問を、メジャーがあればその場で解決できます。
特に、披露宴会場の広さは、ゲストの人数に対してゆったりとくつろげる空間を確保できるかどうかの重要な指標となります。
例えば、最大収容人数ぎりぎりの会場だと、ゲストの移動スペースが狭くなったり、テーブル間の距離が近すぎたりして、窮屈な印象を与えてしまう可能性があります。
逆に、広すぎる会場を選んでしまうと、ゲストがまばらになり、寂しい印象になってしまうことも。
また、高砂(新郎新婦の席)のスペースも意外と重要です。
装飾にこだわりたい場合や、写真撮影の際にゆとりを持たせたい場合は、メジャーで高砂周りのスペースを測っておくと良いでしょう。
さらに、控え室の広さや、親族控室の設備、ゲスト用トイレの数なども、メジャーで確認しておくと安心です。
特に、親族控室は、ゆったりとくつろげるスペースがあるか、授乳やおむつ交換ができる設備があるかなども確認しておくと、ゲストへの配慮として喜ばれます。
私の知人のカップルは、メジャーを持参し忘れてしまい、後日「あの壁からあの壁まで、あと1メートル広かったら、あの円卓をもう1つ置けたのに…」と悔やんでいました。
「なんとなく広い」という感覚ではなく、「具体的にこのくらいの広さ」という数値を把握しておくことの重要性を、彼らの話を聞いて改めて実感しました。
特に、階段の幅や、エントランスから会場までの動線なども、メジャーで測っておくと、車椅子での移動や、大きな装飾の搬入が可能かどうかの判断材料にもなります。
スマホのカメラで「細部まで記録」する
メジャーと並んで、スマホのカメラは必須の持ち物です。
会場全体の雰囲気はもちろん、細部に至るまで、気になる箇所はすべて写真に収めましょう。
特に、装飾のアイデアに繋がるような、会場の設え(しつらえ)や、照明の雰囲気、壁や天井のデザインなどは、後で見返したときに非常に役立ちます。
例えば、壁に飾られた絵画や、天井から吊るされたシャンデリア、窓からの景色など、会場ならではの魅力的なポイントを写真で記録しておけば、後で装飾や演出のインスピレーション源になります。
さらに、実際に使用されるテーブルや椅子のデザイン、カトラリーやグラスの雰囲気なども、写真で記録しておくと、後々のテーブルコーディネートの参考になります。
「このテーブルクロスに合う装花はどんな色味だろう?」とか、「このグラスに合うドリンクメニューを考えよう」といった具体的なイメージが湧きやすくなります。
私が以前担当したお客様で、下見の際に「なんとなく綺麗」という印象だけで会場を決めてしまった方がいらっしゃいました。
後日、装花やテーブルコーディネートの打ち合わせで、「あの会場の壁の色に合う花の色は?」とか、「あの床のタイルに映えるテーブルクロスは?」といった具体的な相談を受けた際に、写真がほとんどなく、会場の細部を思い出せなかったために、イメージ通りのコーディネートが難しくなってしまったという経験があります。
だからこそ、「なんとなく」ではなく、「具体的に」会場の魅力を記録しておくことが、後々の打ち合わせをスムーズに進める鍵となるのです。
また、備品(プロジェクター、音響設備、マイクなど)の場所や、使用方法がわかるような写真も撮っておくと、演出の相談をする際に役立ちます。
例えば、「この壁にプロジェクターで映像を映したいのですが、可能ですか?」といった質問をする際に、現場の状況がわかる写真があれば、会場側も的確なアドバイスをしやすくなります。
スマホのボイスレコーダーで「話した内容」を逃さない
会場の担当者の方から、様々な説明を受けますよね。
その場でメモを取るのも良いですが、スマホのボイスレコーダーを活用すれば、より詳細な情報を正確に記録できます。
特に、料金体系、オプション内容、キャンセルポリシー、アレルギー対応など、後で確認したい重要な情報は、担当者の方の言葉そのままを記録しておくことで、誤解や記憶違いを防ぐことができます。
私は、以前担当したカップルが、下見の際に担当者の方の説明を熱心に聞きすぎて、メモを取る時間がなくなってしまったという状況に遭遇しました。
後日、料金について疑問が生じた際に、「あの時、担当者の方が何と言っていたか思い出せない…」と困っていたのを見て、「話した内容をそのまま記録できるボイスレコーダーの重要性」を痛感しました。
さらに、会場の雰囲気や、担当者の方の対応についても、後で冷静に振り返るための貴重な情報源となります。
例えば、「この担当者の方は、こちらの質問に丁寧に答えてくれたな」とか、「この会場の雰囲気は、私たちのイメージに合っているな」といった、感情的な部分も含めて記録しておくことで、後で客観的に会場を比較検討する際の判断材料になります。
「後で役立つ情報」を整理するための記録グッズ
下見の際に入手した情報は、後々整理して比較検討する必要があります。
そのためには、いくつかの記録グッズが役立ちます。
これらを活用することで、複数の会場を効率的に比較し、自分たちに最適な会場を見つけることができます。
ノートとペンで「自分たちの言葉」で記録する
スマホのボイスレコーダーも便利ですが、やはり自分の手で書き込むことにも大きな意味があります。
ノートとペンがあれば、会場の担当者の方の説明を聞きながら、自分たちの言葉で要点をまとめたり、疑問点を書き出したりすることができます。
特に、「自分たちが重視するポイント」を意識して書き込むことで、会場ごとの特徴や強みが明確になり、比較検討がしやすくなります。
例えば、「ゲストの満足度を最優先したい」というカップルであれば、料理の味や量、ドリンクの種類、スタッフの対応などを重点的にメモするでしょう。
一方、「オリジナリティあふれる演出をしたい」というカップルであれば、会場の自由度や、持ち込み可能なアイテム、外部業者との連携などを詳しく記録するはずです。
私が以前担当したカップルは、下見の際に、会場のパンフレットに直接書き込んでいたのですが、後で他の会場の情報と混ざってしまい、混乱していました。
会場ごとに専用のノートを用意したり、項目を統一して書き込むようにアドバイスしたところ、後々の比較検討が格段にスムーズになったとのことでした。
「自分たちの言葉で、自分たちが重視するポイントを記録する」という作業は、会場選びの軸を明確にするための非常に重要なプロセスなのです。
さらに、会場の担当者の方に質問したいことを事前にリストアップしておき、ノートに書き込んでおくこともおすすめです。
下見の当日に、質問したいことを忘れてしまったり、聞きたいことがあったのに、タイミングを逃してしまったりすることを防ぐことができます。
会場のパンフレットや資料を「整理」する
下見をすると、ほとんどの会場でパンフレットや資料をもらえます。
これらは、会場の基本情報、料金プラン、料理のメニュー、装飾の事例などが記載されており、非常に参考になります。
しかし、複数の会場を回ると、これらの資料がどんどん溜まっていき、どれがどれだか分からなくなってしまうことも。
そこで、会場ごとにクリアファイルを用意したり、インデックスを付けたりして、資料を整理しておくことをおすすめします。
「この会場の料理は魅力的だけど、料金が少し高いな」「この会場の雰囲気は最高だけど、アクセスが少し不便だな」といった、自分たちの評価をパンフレットの余白に書き込んでおくのも良いでしょう。
私が以前担当したお客様は、下見の際にパンフレットをそのまま持ち帰るだけでなく、「この会場のこの写真が気に入ったから、このページをコピーしておこう」とか、「この会場のこのプランは、私たちの希望に合っているから、この部分を切り抜いておこう」といった工夫をしていました。
資料をただ持ち帰るだけでなく、自分たちにとって重要な情報だけをピックアップし、整理しておくことで、後々の会場比較が格段に効率的になります。
「持ち帰り用」の質問リストを作成する
会場の担当者の方に、その場で全てを質問しきれないこともあります。
事前に「持ち帰り用」の質問リストを作成しておき、下見の際に担当者の方に確認し、回答を記録できるようにしておくと安心です。
例えば、「アレルギー対応の具体的な内容」「持ち込み可能なアイテムのリスト」「キャンセル料が発生するタイミング」など、後から確認したい、あるいは、その場で回答を得にくい質問をまとめておくと、効率的に情報を収集できます。
私が以前担当したカップルは、下見の際に、担当者の方に「この会場で、〇〇という演出は可能ですか?」と質問したものの、その場で明確な回答が得られず、後日になって「やっぱりその演出は難しい」という返答が来てしまい、がっかりしていました。
事前に「〇〇という演出は可能ですか?」といった質問をリストアップしておき、担当者の方に「後日、確認して回答いただけますでしょうか?」とお願いしておくことで、このような事態を防ぐことができます。
「その場で即答できないこと」についても、きちんと記録を残し、後日回答を得られるように段取りをしておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
「客観的な視点」を保つための冷静さの重要性
結婚式場選びは、感情的になりやすい場面でもあります。
会場の雰囲気や、担当者の方の熱意に流されず、常に冷静な視点を保つことが、後悔しない会場選びの鍵となります。
「理想」と「現実」のギャップを冷静に見極める
結婚式に対する理想は、誰しも持っているものです。
しかし、理想ばかりを追い求めてしまうと、予算や、会場の制約といった現実的な側面を見失ってしまうことがあります。
下見の際には、「自分たちの予算内で、どこまで理想を叶えられるのか」という現実的な視点を常に持ち、冷静に会場のプランやオプション内容を検討することが大切です。
例えば、「憧れのチャペルで結婚式を挙げたい」という理想があったとしても、そのチャペルが予算オーバーであったり、ゲストの人数に合わないほど小さかったりする場合、他の選択肢も検討する必要があります。
「この会場のこの部分だけは譲れない」という譲れないポイントを明確にしつつ、それ以外の部分では、ある程度の柔軟性を持つことが、後悔しない会場選びに繋がります。
私が以前担当したカップルは、当初、非常に高額な会場を希望されていましたが、予算との兼ね合いから、いくつかの会場で妥協点を見つけていきました。
「この会場のこの雰囲気は叶えられないけれど、料理は最高だから、この会場にしよう」というように、自分たちの優先順位を明確にし、冷静に判断された結果、結果的に満足度の高い結婚式を実現できたようです。
「理想」と「現実」のギャップを冷静に見極め、自分たちにとって最もバランスの取れた会場を選ぶことが、後々の満足度に大きく影響します。
「第三者の意見」を冷静に聞く姿勢を持つ
結婚式場選びは、新郎新婦だけでなく、ご家族やご友人など、周りの意見も参考にしたいところです。
しかし、あまりにも多くの意見を聞きすぎると、かえって迷ってしまい、自分たちの本当に望むものが分からなくなることもあります。
下見の際には、信頼できる数名の方に同行してもらい、客観的な意見を聞くことをおすすめします。
ただし、最終的な決定権は、あくまで新郎新婦にあるということを忘れずに、冷静に判断することが重要です。
例えば、ご両親は「伝統的な雰囲気の会場が良い」という意見を持っていたとしても、新郎新婦は「モダンでスタイリッシュな会場が良い」と考えているかもしれません。
それぞれの意見を尊重しつつも、自分たちの結婚式に最もふさわしい会場は何か、という視点を忘れずに、冷静に判断する必要があります。
私が以前担当したカップルは、ご両親の意見を全面的に