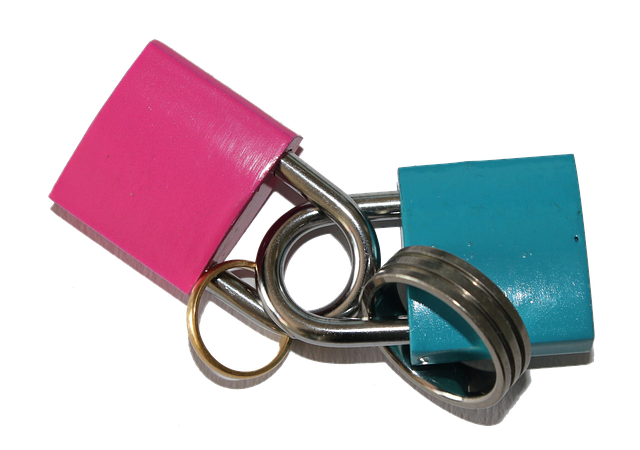結婚式の招待状を受け取った時、嬉しい気持ちと共に「メッセージをどう書こうかな?」と少し悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大切な友人や家族、お世話になっている方へのお祝いの気持ちを伝える最初の機会だからこそ、失礼なく、そして心からの「おめでとう」を届けたいですよね。
この記事では、あなたが自信を持って素敵なメッセージを送るための「送る側の結婚式招待状メッセージの書き方ポイント」を、具体的な例を交えながら分かりやすくご紹介します。
形式的なマナーから、相手に合わせた心温まる一言まで、メッセージ作成のヒントがきっと見つかるはずです。
結婚式招待状メッセージ、なぜ重要?送る前に知るべき基本
結婚式の招待状を受け取った際の返信ハガキに書くメッセージは、単なる出欠の連絡手段ではありません。
それは、新郎新婦へのお祝いの気持ちを伝える最初の、そして大切な機会です。
あなたが心を込めて書いたメッセージは、新郎新婦にとって結婚準備の疲れを癒し、結婚式当日への期待をさらに高めてくれる宝物になります。
特に、招待状の準備は新郎新婦にとって多くの時間と労力がかかるもの。
その大変な作業を経て送られた招待状に対し、すぐにお祝いの言葉と共に返信することは、新郎新婦への感謝と敬意を示す行為でもあります。
形式的な返信だけでなく、短い一言でもメッセージを添えることで、あなたの「おめでとう」の気持ちがより鮮明に伝わります。
メッセージを書く前に、まずは返信ハガキの基本的なマナーや、お祝いのメッセージならではの注意点を確認しておきましょう。
これらを知っておくことで、安心してメッセージ作成に取り組むことができます。
新郎新婦があなたのメッセージを読んだ時に、思わず笑顔になるような、そんな温かい言葉を選びたいですね。
メッセージに込める「おめでとう」の気持ち
結婚式の招待状にメッセージを書く最大の目的は、何よりも新郎新婦への心からの祝福を伝えることです。
もちろん、出欠の返信は事務的に必要な情報ですが、メッセージ欄に書く言葉は、あなたの人間性やお二人の関係性を映し出す鏡のようなもの。
「結婚おめでとう!」というシンプルな言葉でも、そこにどのような気持ちを込めるかで、伝わり方は大きく変わります。
例えば、長年の友人であれば、これまでの二人の道のりを振り返りながら、今日の喜びを分かみ合う気持ちを表現するのも良いでしょう。
職場の同僚や上司であれば、日頃の感謝と共に、公私にわたる幸せを願う気持ちを丁寧に伝えます。
メッセージを書く際は、まず新郎新婦の顔を思い浮かべ、どんな言葉で自分の喜びやお祝いの気持ちを伝えたいかを考えてみましょう。
形式に囚われすぎず、素直な気持ちを表現することが大切です。
あなたのメッセージが、お二人の新しい門出を祝う温かいエールとなることを願って、言葉を選んでみてください。
返信ハガキへのメッセージ欄の基本マナー
返信ハガキのメッセージ欄に書く際には、いくつかの基本的なマナーがあります。
まず、メッセージを書くスペースは限られていますので、簡潔にまとめることが重要です。
返信ハガキには、宛名の「行」や「宛」を二重線で消して「様」に書き換えたり、自分の名前の下の「行」を消すといった修正箇所がありますが、これらの修正を先に行い、次にメッセージを書くのが一般的な流れです。
メッセージを書く筆記用具は、黒または濃い青のインクのペンを使用するのが望ましいとされています。
消えるボールペンは避けましょう。
メッセージを書く前に、鉛筆などで下書きをすると、バランスを確認したり、書き間違えを防ぐことができます。
特に、普段書き慣れない毛筆や筆ペンで書きたい場合は、練習してから書くことをお勧めします。
また、ハガキを汚してしまったり、書き損じたりした場合に備えて、予備のハガキをもらっておくか、自分で新しいハガキを用意して書き直す方が丁寧です。
メッセージは、新郎新婦が受け取って気持ちよく読めるように、丁寧に、そして心を込めて書きましょう。
句読点や忌み言葉を避ける理由
結婚式の招待状のメッセージでは、句読点(「、」「。
」)を使用しないのが一般的なマナーとされています。
これは、句読点が「区切り」や「終わり」を連想させるため、結婚というおめでたいことにはふさわしくないと考えられているからです。
お祝い事が「滞りなく」「途切れることなく」続くように、という願いが込められています。
句読点の代わりに、スペースを空けたり、改行したりして文章の区切りを示すと良いでしょう。
また、「忌み言葉」と呼ばれる、結婚や門出にふさわしくない言葉も避ける必要があります。
例えば、「別れる」「離れる」「終わる」「切れる」「壊れる」「冷える」「去る」「戻る」「再び」「重ね重ね」「くれぐれも」などが挙げられます。
これらは不幸や別れ、再婚などを連想させるため、お祝いの席では使わないように注意が必要です。
「終わる」という言葉を避けたい場合は、「結びとなりますが」ではなく「末筆ではございますが」といった言葉に言い換えられます。
また、「重ね重ね」は「ますます」や「一層」に、「くれぐれも」は「どうぞ」や「皆様お揃いで」などに置き換えることができます。
これらのマナーは、新郎新婦への配慮と、お祝いの気持ちを純粋に伝えるためのものです。
言葉遣いに少し気を使うだけで、より洗練された、心遣いの感じられるメッセージになります。
相手別!心に響くメッセージの書き分け方
結婚式の招待状のメッセージは、送る相手との関係性によって書き分けることが大切です。
親しい友人、職場の同僚や上司、そして親族。
それぞれにふさわしい言葉遣いや内容があります。
形式的なメッセージだけでは、せっかくの機会にもったいないですよね。
相手とのこれまでの関係性や、結婚に対するお二人の思いなどを考慮して言葉を選ぶことで、よりパーソナルで心に響くメッセージになります。
例えば、長い付き合いの友人には、二人の馴れ初めやプロポーズのエピソードに触れたり、共通の知人との思い出を交えたりするのも良いでしょう。
職場の方には、日頃の感謝や尊敬の念を伝えつつ、今後の活躍や幸せを願う言葉を添えます。
親族には、家族が増えることへの喜びや、これまでの成長を見守ってきた温かい気持ちを伝えます。
相手との関係性を深く考え、どのような言葉が一番喜ばれるかを想像しながら書くことが、心に響くメッセージを作成する鍵です。
ここでは、代表的な相手別に、メッセージの書き分け方のポイントをご紹介します。
親しい友人へ、飾らない言葉で伝える祝福
親しい友人へのメッセージは、堅苦しい言葉遣いよりも、普段の関係性を反映させた飾らない言葉で伝えるのが一番です。
ただし、お祝いの場であること、そして返信ハガキというフォーマルな形式であることは意識しつつ、丁寧さと親しみのバランスを取りましょう。
メッセージに共通の思い出やエピソードを盛り込むと、よりパーソナルで心温まるメッセージになります。
例えば、「〇〇と初めて会ったのは大学のサークルだったね。
いつも明るい〇〇が素敵なパートナーと出会って、本当に嬉しいです」「二人で旅行に行った時の話、懐かしいね。
これからは△△さんと一緒に、もっともっと楽しい思い出を作ってね」のように、具体的なエピソードに触れることで、メッセージに深みが増します。
また、相手の個性や人柄に触れるのも良いでしょう。
「いつも周りを明るくする〇〇らしい、笑顔いっぱいの結婚式になるんだろうなと今から楽しみにしています」といった言葉は、相手への理解と期待が伝わります。
「〇〇のウェディングドレス姿、絶対に見たい!」や「結婚式で会えるのを楽しみにしているね!」など、結婚式当日への期待感を伝える一言も喜ばれます。
メッセージの最後には、新生活への応援の言葉を添えて締めくくりましょう。
職場の上司・同僚へ、丁寧さと敬意を込めて
職場の上司や同僚へのメッセージは、相手との関係性によって適切な言葉遣いが異なります。
上司へは、日頃の感謝や尊敬の念を込めて、より丁寧な言葉を選びましょう。
例えば、「この度はお招きいただき誠にありがとうございます」といった丁寧な冒頭の挨拶は必須です。
日頃お世話になっていることに触れ、「いつも温かいご指導を賜り感謝申し上げます」といった言葉を添えるのも良いでしょう。
その上で、結婚を心から祝福する言葉を続けます。
「〇〇課長が素敵な伴侶と巡り会われ、心よりお慶び申し上げます」といった表現が適切です。
今後の活躍や幸せを願う言葉、「公私ともにますます充実されることをお祈りいたします」といった一言を添えると、より丁寧な印象になります。
同僚へのメッセージは、関係性によってはもう少し親しみを込めた表現も可能ですが、基本的には丁寧な言葉遣いを心がけます。
共通のプロジェクトや部署での思い出に触れるのも良いですが、プライベートに踏み込みすぎないように注意しましょう。
「〇〇さんと一緒に仕事ができて、いつも学ぶことが多く感謝しています。
素敵なご家庭を築かれることと思います」といった、仕事と関連付けた祝福も自然です。
いずれの場合も、忌み言葉や句読点のマナーは守り、失礼のないように細心の注意を払いましょう。
親族へ、親愛の情を伝えるメッセージ
親族へのメッセージは、血縁関係やこれまでの付き合いの深さによって言葉遣いが変わりますが、共通しているのは、家族が増えることへの喜びや、これまでの成長を見守ってきた温かい気持ちを伝えることです。
兄弟姉妹やいとこなど、比較的年齢が近い親族であれば、友人へのメッセージに近い親愛を込めた表現も可能でしょう。
「〇〇が結婚するなんて、自分のことのように嬉しいよ!」「小さい頃から見てきた〇〇がこんなに立派になって、本当に感慨深いです」といった、個人的な感情を率直に伝える言葉は、親族ならではの温かさがあります。
甥や姪など、目下の親族へのメッセージであれば、成長を喜ぶと共に、これからの人生へのエールを送るような言葉を選びます。
「〇〇が素敵な伴侶と出会い、新しい人生を歩み始めること、心から嬉しく思います。
二人の未来が光り輝くものでありますように。
」といった、温かい応援のメッセージが喜ばれるでしょう。
祖父母や叔父叔母など、目上の親族へは、丁寧な言葉遣いを基本としつつ、家族としての喜びを伝えます。
「この度はお招きいただきありがとうございます。
〇〇さんが素敵な伴侶と巡り会われ、家族一同大変喜んでおります。
」といった、家族としての連帯感を示す言葉も良いでしょう。
親族間の関係性を考慮し、最も自然で心温まる言葉を選ぶことが大切です。
遠方のゲストや特別な事情がある場合
招待状を送ってくれた相手が遠方に住んでいる場合や、自分が遠方から参加する場合、または小さな子供がいる、妊娠中である、アレルギーがあるなど、特別な事情を抱えている場合は、メッセージにその旨を丁寧に書き添えることで、新郎新婦への配慮を示すことができます。
遠方からの招待への返信であれば、まず招待してくれたことへの感謝を伝えます。
「遠方よりお招きいただき、誠にありがとうございます。
」といった言葉を添え、出席する場合は「喜んで出席させていただきます。
」と続けます。
遠方からの移動や宿泊について触れる場合は、「前日より上京(または帰省)させていただきます」など、具体的な行動を簡潔に伝えることで、新郎新婦が当日の段取りをイメージしやすくなります。
特別な事情がある場合は、メッセージ欄に簡潔に、そして丁寧に書き添えます。
例えば、小さな子供を連れて行く場合は「恐れ入りますが、子供(〇歳)も一緒に参加させていただけますでしょうか。
」、アレルギーがある場合は「誠に申し訳ありませんが、〇〇(具体的な食材)にアレルギーがございます。
もしご配慮いただけましたら幸いです。
」といったように、具体的に、かつ新郎新婦の手間を考慮した謙虚な姿勢で伝えることが重要です。
これらの情報は、新郎新婦がゲストへの配慮や当日の準備を進める上で大変役立ちますので、忘れずに、かつ失礼のないように伝えましょう。
状況別!メッセージ例文とアレンジのヒント
結婚式の招待状への返信メッセージは、出席する場合、欠席する場合、そして返信が遅れてしまった場合など、状況によって書く内容が変わってきます。
それぞれの状況に応じて、失礼なく、かつ心からの気持ちを伝えるためのメッセージのポイントがあります。
単に「出席します」「欠席します」と伝えるだけでなく、そこに丁寧な言葉遣いや、相手への配慮を込めることで、より気持ちが伝わる返信になります。
また、メッセージに少しアレンジを加えることで、定型文にはないあなたらしさや、新郎新婦への特別な思いを表現することができます。
例えば、出席する場合であれば、結婚式当日への期待感を具体的に表現したり、新郎新婦の幸せを願う具体的なエピソードに触れたりすることで、メッセージがぐっとパーソナルなものになります。
欠席する場合でも、ただ欠席を伝えるだけでなく、出席できないことへの残念な気持ちや、改めてお祝いしたい気持ちを丁寧に伝えることが大切です。
ここでは、よくある状況別のメッセージ例文をいくつかご紹介し、さらにあなたらしいメッセージにアレンジするためのヒントもお伝えします。
出席する場合のメッセージ例文とプラスアルファの添え書き
結婚式に出席する場合のメッセージは、まず招待してくれたことへの感謝と、結婚のお祝いの言葉から始めます。
「この度はお招きいただき誠にありがとうございます。
〇〇さんの結婚の知らせを受け、自分のことのように嬉しく思っております。
」といった丁寧な言葉遣いが基本です。
次に、喜んで出席する旨を伝えます。
「喜んで出席させていただきます。
」「ぜひ出席させていただきたく存じます。
」など、前向きな意思表示をします。
その上で、結婚式当日への期待や、新郎新婦の未来への祝福を添えることで、より温かいメッセージになります。
例えば、「お二人の晴れ姿を拝見できること、今からとても楽しみにしております。
」「きっと笑顔あふれる素晴らしい結婚式になることと思います。
」といった言葉や、「お二人の末永いお幸せを心よりお祈り申し上げます。
」といった祝福の言葉を添えます。
さらにプラスアルファとして、新郎新婦との具体的なエピソードや、二人の人柄に触れる一言を加えると、メッセージに深みが増します。
「いつも△△さんのことを大切にしている〇〇さんの姿を見て、いつかこんな日が来ると思っていました。
本当に素敵なお二人ですね。
」のように、具体的なエピソードを交えると、オリジナリティあふれるメッセージになります。
もし、結婚式の準備で手伝えることがあれば、「何かお手伝いできることがあれば、いつでもお声がけください」といった言葉を添えるのも、新郎新婦にとっては心強いサポートになります。
残念ながら欠席する場合の失礼にならない伝え方
結婚式に残念ながら出席できない場合は、まず招待してくれたことへの感謝を伝え、結婚のお祝いの言葉を述べた上で、丁寧な言葉遣いで欠席する旨を伝えます。
欠席の理由を具体的に書く必要はありませんが、「やむを得ない事情により」「どうしても都合がつかず」といった表現で、出席できないことへの残念な気持ちを伝えるのがマナーです。
「この度はお招きいただき誠にありがとうございます。
〇〇さんの結婚の知らせを受け、心よりお慶び申し上げます。
誠に残念ながら、やむを得ない事情により欠席させていただきます。
」といった流れが一般的です。
欠席する場合でも、出席できないことへの残念な気持ちと、お二人の幸せを願う気持ちをしっかりと伝えることが重要です。
「お二人の晴れ姿を拝見できず、大変残念に思っております。
」「当日のご結婚式が素晴らしいものとなりますよう、遠方よりお祈り申し上げます。
」といった言葉を添えます。
さらに、改めてお祝いしたい気持ちを伝えることで、新郎新婦への配慮を示すことができます。
「改めてお祝いさせていただければ幸いです。
」「後日改めてご挨拶に伺わせていただきます。
」といった一言を添えると、丁寧な印象になります。
もし、電報やプレゼントなどを贈る予定があれば、その旨を伝えることで、お祝いの気持ちがより伝わります。
返信が遅れてしまった時の誠意あるメッセージ
結婚式の招待状の返信期限を過ぎてしまった場合は、まず返信が遅れてしまったことへのお詫びを丁寧に伝えることが最も重要です。
「返信が遅くなりまして、誠に申し訳ございません。
」と、冒頭で率直に謝罪の言葉を述べます。
返信が遅れた理由を簡潔に述べることもありますが、曖昧な表現にとどめるか、特に触れない方が良い場合もあります。
例えば、「確認が遅れてしまい、大変申し訳ございません。
」といった表現に留めることも可能です。
その上で、結婚のお祝いの言葉と、出席または欠席の意思表示を明確に伝えます。
「この度はお招きいただき、心よりお慶び申し上げます。
つきましては、喜んで出席させていただきます。
」のように、遅れてしまったことへの謝罪とお祝い、そして返信内容を明確に記述します。
欠席の場合も同様に、「誠に申し訳ございませんが、欠席させていただきます。
」と伝えます。
返信が遅れたことで新郎新婦に迷惑をかけてしまったことへの配慮として、より一層丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
メッセージの最後には、改めてお祝いの言葉や、お二人の幸せを願う言葉を添えて締めくくります。
子供連れやアレルギー対応をお願いする場合
結婚式に子供を同伴したい場合や、食事にアレルギーがある場合は、返信ハガキのメッセージ欄を利用して、その旨を丁寧に伝えることができます。
ただし、メッセージ欄は限られたスペースですので、簡潔かつ分かりやすく記述することが重要です。
まず、通常のお祝いと出席のメッセージを書いた上で、末尾に追記する形でお願いをします。
子供連れをお願いする場合は、「恐れ入りますが、子供(氏名、〇歳)も一緒に参加させていただけますでしょうか。
」といったように、同伴する子供の氏名と年齢を添えると、新郎新婦が席次や食事の準備をする上で助けになります。
アレルギーがある場合は、「誠に申し訳ございませんが、〇〇(具体的な食材名)にアレルギーがございます。
もしご配慮いただけましたら幸いです。
」といったように、具体的な食材名を伝え、謙虚な姿勢でお伝えします。
どちらの場合も、「お手数をおかけいたしますが」「ご無理のない範囲で」といった相手への配慮を示す言葉を添えることが大切です。
これらの情報は、新郎新婦がゲスト全員に気持ちよく過ごしてもらうために必要な準備に関わることですので、早めに、そして正確に伝えることが望ましいです。
返信ハガキ以外のメッセージの機会
結婚式に関するメッセージを送る機会は、返信ハガキだけではありません。
結婚祝いに添えるメッセージカード、結婚式当日に送る祝電、そして受付で渡すメッセージなど、様々な場面でメッセージを伝える機会があります。
これらのメッセージは、返信ハガキとはまた違った形で、新郎新婦へのお祝いの気持ちや、結婚式当日を共に喜びたいという気持ちを伝えることができます。
それぞれにふさわしいメッセージの内容や形式がありますので、場面に合わせて適切な言葉を選びましょう。
例えば、結婚祝いに添えるメッセージカードは、プレゼントと共に贈るため、より個人的で温かいメッセージを添えることができます。
祝電は、結婚式当日に会場に届けられるため、欠席する場合や、よりフォーマルにお祝いを伝えたい場合に適しています。
受付で渡すメッセージは、当日の新郎新婦へ直接的な祝福や、感謝の気持ちを伝える絶好の機会です。
これらのメッセージも、返信ハガキと同様に、句読点や忌み言葉に注意しつつ、心からの「おめでとう」を伝えることが最も重要です。
結婚祝いに添えるメッセージカード
結婚祝いとしてプレゼントやご祝儀を贈る際に、メッセージカードを添えると、お祝いの気持ちがより一層伝わります。
メッセージカードは、返信ハガキよりも自由度が高く、よりパーソナルなメッセージを書くことができます。
カードのデザインもお祝いにふさわしい華やかなものを選ぶと良いでしょう。
メッセージの内容は、まず結婚のお祝いの言葉から始めます。
「ご結婚誠におめでとうございます!」といったストレートな祝福の言葉は、何度聞いても嬉しいものです。
次に、プレゼントを選んだ理由や、新郎新婦の新しい生活への応援の言葉を添えます。
例えば、「お二人の新居にぴったりのものが見つかったので、贈らせていただきます。
お二人の毎日が、より一層明るく楽しいものになりますように。
」といったように、プレゼントに込めた思いを伝えることで、メッセージがより温かいものになります。
共通の思い出や、お二人の人柄に触れる一言を加えるのも良いでしょう。
「いつも笑顔の素敵なお二人を見ていると、こちらまで幸せな気持ちになります。
これからも末永くお幸せに!」といった言葉は、新郎新婦への心からの祝福が伝わります。
メッセージカードは、短い一言でも心を込めて書くことが大切です。
祝電としてメッセージを送る場合
結婚式に欠席する場合や、遠方で参列できない場合、またはよりフォーマルにお祝いを伝えたい場合に、祝電を送るという選択肢があります。
祝電は、結婚式当日に会場に届けられ、披露宴で読み上げられることもあります。
そのため、結婚式にふさわしい丁寧な言葉遣いを心がける必要があります。
祝電には、NTTなどが提供する電報サービスを利用するのが一般的で、様々な台紙や文例が用意されています。
基本的な構成は、まずお祝いの言葉、次に新郎新婦の門出を祝う言葉、そして今後の幸せを願う言葉となります。
祝電の文例を参考に