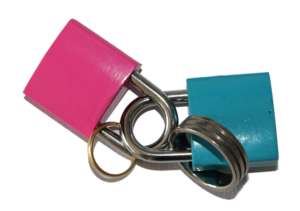結婚式の招待状は、お二人の大切な門出をゲストにお知らせする最初のおもてなしです。
中でも、招待状に添える「本人宛て」のメッセージは、受け取ったゲストにとって特別な意味を持つものです。
印刷された定型文だけでなく、新郎新婦からの温かい手書きのメッセージがあるだけで、結婚式への期待感はぐっと高まります。
この記事では、本人宛てに送る結婚式招待状メッセージの基本と例文を、関係性別に詳しくご紹介します。
マナーを守りつつ、心を込めたメッセージを贈るためのヒントが満載ですので、ぜひ最後まで読んで、ゲスト一人ひとりに喜ばれる招待状を作成してください。
本人宛てメッセージが結婚式招待状を特別なものにする理由
結婚式の招待状は、新郎新婦がゲストに「私たちの晴れ姿を見に来てください」と正式にお願いする大切なツールです。
その中でも、招待状の本文とは別に添えられる本人宛てのメッセージは、受け取る方にとって格別な喜びとなります。
なぜなら、それは新郎新婦が自分のために時間を割いて、特別な言葉を選んでくれた証だからです。
なぜ「本人宛て」メッセージが必要なのか
招待状の本文は、結婚式の日時や場所といった案内が中心で、誰に送る場合でも内容は基本的に同じです。
しかし、結婚式に招くゲストは、友人、親戚、会社の上司や同僚など、お二人との関係性が多岐にわたります。
一人ひとりに向けたメッセージを添えることで、「あなたに結婚式に来てほしい」という強い気持ちや、日頃の感謝、これまでの思い出などを具体的に伝えることができます。
これは、受け取ったゲストが「自分は大切にされている」「特別な存在として招待された」と感じる瞬間であり、結婚式への参加を前向きに検討する大きなきっかけとなります。
特に、遠方からのゲストや、忙しい中時間を割いてくれる方にとっては、メッセージがあることで負担をかけてしまうことへの配慮や感謝の気持ちが伝わり、より一層出席したいという気持ちになるでしょう。
単なる事務連絡ではなく、お二人の温かい想いが伝わるコミュニケーションツールとして、本人宛てメッセージは非常に重要な役割を果たします。
基本の構成要素とマナー
本人宛てメッセージには、明確な決まりがあるわけではありませんが、一般的に盛り込むと良いとされる要素と、守るべきマナーがあります。
基本的な構成としては、まず時候の挨拶や安否を気遣う言葉から始めます。
次に、結婚の報告と結婚式への招待の言葉を改めて伝えます。
そして、ゲストとの関係性に応じた個人的なメッセージ(感謝の言葉、思い出、今後の付き合いについてなど)を綴り、最後に結婚式当日を楽しみにしている気持ちや結びの言葉で締めくくります。
マナーとしては、まず手書きで書くのが基本です。
丁寧な文字で書くことで、より誠意が伝わります。
また、丁寧な言葉遣いを心がけることも大切です。
特に目上の方やあまり親しくない方へ送る場合は、失礼のないように細心の注意を払いましょう。
さらに、結婚式というお祝い事に関するメッセージでは、句読点を使用しない慣習があります。
「終止符を打たない」「幸せが途切れない」という意味合いから、句読点の代わりにスペースを空けるのが一般的です。
これは必須のマナーではありませんが、知っておくとより丁寧な印象になります。
避けるべき言葉や表現
結婚祝いのメッセージと同様に、結婚式の招待状に添えるメッセージでも、避けるべき言葉や表現がいくつか存在します。
最も注意が必要なのは、「忌み言葉」と「重ね言葉」です。
忌み言葉とは、「別れる」「切れる」「終わる」「冷える」「去る」「離れる」「破れる」「壊れる」など、別れや不幸を連想させる言葉です。
これらの言葉は、お祝いの席にはふさわしくありません。
また、重ね言葉とは、「重ね重ね」「たびたび」「いよいよ」「重々」「くれぐれも」など、再婚を連想させる言葉です。
こちらも避けるのが一般的です。
ただし、現代では気にしない方も増えていますが、特に目上の方やマナーを重んじる方へ送る場合は注意が必要です。
これらの言葉を使わないように意識するだけで、メッセージ全体の印象がぐっと良くなります。
メッセージを書く前に、一度避けるべき言葉のリストを確認しておくと安心です。
もし不安な場合は、別の言葉に言い換えたり、表現を変えたりする工夫をしましょう。
例えば、「お忙しいところ恐縮ですが」の代わりに「ご多忙中大変恐縮ではございますが」とするなど、より丁寧な表現を選ぶことも大切です。
関係性別!心に響くメッセージの書き方と例文
本人宛てメッセージは、送る相手との関係性によって内容を書き分けることが非常に重要です。
親しい友人にはフレンドリーに、目上の方には敬意を込めて、家族には感謝の気持ちを込めて、といったように、相手に合わせた言葉を選ぶことで、メッセージはより心に響くものになります。
ここでは、主な関係性別にメッセージの書き方と具体的な例文をご紹介します。
親しい友人へ贈るメッセージ
親しい友人へのメッセージは、形式ばらずに、これまでの二人の関係性や共通の思い出を盛り込むのがおすすめです。
結婚の報告を改めて伝えるとともに、結婚式に来てほしいという素直な気持ちを伝えましょう。
メッセージのトーンは、普段話しているような親しみやすい言葉遣いで大丈夫です。
ただし、丁寧すぎる必要はありませんが、最低限のマナーは守るようにしましょう。
例えば、「〇〇(相手の名前)へ」「〇〇(相手の名前)、元気にしてる?」といった呼びかけから始め、「この度、〇〇さんと結婚することになりました」「結婚式を行うことになったので、ぜひ来てほしいな」と続けます。
その後に、二人の思い出や、友人への感謝の気持ち、結婚式への期待などを自由に綴ります。
「〇〇とは学生時代からの友達だから、結婚式に来てくれると本当に心強いよ」「いつも相談に乗ってくれてありがとう。
結婚の報告ができて嬉しいです」「〇〇が楽しんでくれるような式にしたいと思ってるから、ぜひ来てね!」といった具体的な言葉を入れると、よりパーソナルなメッセージになります。
例文としては、「〇〇へ 元気にしてる? この度、〇〇さんと結婚することになりました。
結婚式を〇月〇日に〇〇で挙げることになったので、ぜひ〇〇に来てほしいな! 〇〇とは高校時代からの長い付き合いだから、一番に報告したくて。
いつも笑わせてくれてありがとう。
〇〇がいてくれたから、今の私がいます。
当日は〇〇にウェディングドレス姿を見てもらえるのが今からすごく楽しみだよ。
ぜひ来てください! 〇〇(差出人名)」のように、具体的なエピソードや感謝の言葉を交えると、より温かいメッセージになります。
目上の方(上司・親戚など)へ贈るメッセージ
会社の上司や恩師、親戚など、目上の方へメッセージを送る場合は、丁寧な言葉遣いを徹底することが最も重要です。
日頃お世話になっていることへの感謝の気持ちを伝え、結婚の報告と結婚式への招待を丁寧に行います。
プライベートなメッセージとはいえ、失礼があってはいけません。
「拝啓 〇〇様」「〇〇部長」のように、相手の氏名や役職名を正確に記載し、「日頃より大変お世話になっております」「ご無沙汰しておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか」といった丁寧な挨拶から始めます。
次に、「この度、〇〇さんと結婚することになり、〇月〇日に結婚式を挙げる運びとなりました」「つきましては、日頃お世話になっております〇〇様にご臨席賜りたく、ご案内申し上げます」と続けます。
個人的なメッセージとしては、「〇〇様には、入社以来大変お世話になり、未熟な私をご指導いただきましたこと、心より感謝申し上げます」「〇〇様のおかげで、今の私があります」など、具体的な感謝の言葉を伝えます。
親戚の方であれば、「〇〇叔父様、〇〇叔母様には、幼い頃から大変可愛がっていただき、心より感謝しております」「結婚のご報告ができましたこと、大変嬉しく思っております」など、これまでの関係性に触れる言葉を入れると良いでしょう。
結びには、「ご多忙中とは存じますが、ぜひご出席いただけますと幸いです」「当日、〇〇様にお会いできますことを心より楽しみにしております」といった言葉を添えます。
例文としては、「拝啓 〇〇部長 日頃より大変お世話になっております。
この度、〇〇さんと結婚することになり、〇月〇日に〇〇で結婚式を挙げる運びとなりました。
つきましては、日頃より大変お世話になっております〇〇部長にご臨席賜りたく、ご案内申し上げます。
入社以来、〇〇部長には温かいご指導を賜り、今の私があるのは〇〇部長のおかげと感謝しております。
ご多忙中とは存じますが、ぜひご出席いただけますと幸いです。
当日、〇〇部長にお会いできますことを心より楽しみにしております。
敬具 〇〇(差出人名)」のように、丁寧さを第一に、感謝の気持ちをしっかりと伝えることを意識しましょう。
兄弟姉妹へ贈るメッセージ
兄弟姉妹へのメッセージは、親しい友人へのメッセージと同様に、比較的フランクなトーンで書くことができます。
しかし、単なる事務連絡ではなく、これまでの感謝や、これからの家族としての関係性について触れると、より心温まるメッセージになります。
普段は照れくさくて言えないような感謝の気持ちや、結婚を機に改めて伝えたい想いをメッセージに込めてみましょう。
「〇〇へ」「〇〇(妹/弟)へ」といった呼びかけから始め、「この度、〇〇さんと結婚することになりました」「結婚式を挙げることになったので、ぜひ来てね!」と伝えます。
個人的なメッセージとしては、「いつも一番近くで支えてくれてありがとう」「〇〇がいてくれたから、安心して結婚を決めることができたよ」「これからは〇〇も家族になるから、どうぞよろしくね」といった言葉を入れると、よりパーソナルなメッセージになります。
幼い頃の思い出や、結婚相手を紹介した時のエピソードなどを加えるのも良いでしょう。
「小さい頃からずっと一緒にいた〇〇に、ウェディングドレス姿を見てもらえるのが嬉しいな」「初めて〇〇を紹介した時、〇〇がすぐに打ち解けてくれて安心したよ」といった具体的な話を入れることで、メッセージに深みが増します。
結びには、「当日、〇〇に会えるのを楽しみにしているよ」「これからも頼りにしています」といった言葉を添えます。
例文としては、「〇〇へ 元気にしてる? この度、〇〇さんと結婚することになりました。
結婚式を〇月〇日に〇〇で挙げることになったので、ぜひ〇〇に来てほしいな! いつも一番近くで私のことを応援してくれてありがとう。
〇〇がいてくれたから、ここまで来れました。
これからは〇〇も家族になるから、どうぞよろしくね。
当日は〇〇に会えるのを楽しみにしているよ! 〇〇(差出人名)」のように、感謝の気持ちとこれからの関係性について触れると、兄弟姉妹ならではの温かいメッセージになります。
メッセージ作成の具体的なステップと押さえたいポイント
本人宛てメッセージの作成は、ゲストへの感謝の気持ちを伝える大切な機会です。
ただ例文を参考に書くだけでなく、いくつかのステップを踏まえ、押さえるべきポイントを意識することで、より心のこもった、失礼のないメッセージを作成することができます。
ここでは、メッセージ作成の具体的な流れと、注意しておきたい点について詳しく解説します。
思いを込める!メッセージ作成前の準備
メッセージを書き始める前に、まずはしっかり準備をすることが大切です。
準備の第一歩は、誰にメッセージを送るかリストアップすることです。
招待状を送るゲスト全員にメッセージを添えるのか、それとも一部のゲストにのみ添えるのかを決め、リストを作成します。
次に、リストアップしたゲスト一人ひとりとの関係性を改めて考え、伝えたいメッセージの内容を検討します。
感謝の気持ち、結婚の報告、結婚式への招待、そしてその人との思い出やエピソードなど、具体的に何を伝えたいかを整理しましょう。
この段階で、伝えたいエピソードや感謝の言葉を書き出しておくと、実際に文章を書く際にスムーズに進められます。
例えば、「〇〇さんには、仕事で困っていた時に助けてもらった」「〇〇とは、大学時代に一緒にサークル活動を頑張った」「〇〇叔母様には、毎年お正月に遊びに行くと温かく迎えてもらった」など、具体的な出来事を思い出してみましょう。
また、メッセージを手書きする場合は、使うペンや便箋、メッセージカードを用意し、下書きをすることも重要です。
ぶっつけ本番で書き始めると、誤字脱字や書き損じの元になります。
下書きをすることで、文章構成を練り直し、伝えたい内容が過不足なく盛り込まれているか確認できます。
清書する際は、丁寧に、心を込めて書くことを意識しましょう。
読みやすく、失礼のない文章にする工夫
メッセージの内容はもちろん大切ですが、それが相手にしっかりと伝わるように、読みやすさや丁寧さにも配慮が必要です。
まず、丁寧な字で書くことを心がけましょう。
字の上手い下手よりも、丁寧に書こうとする気持ちが伝わることが大切です。
次に、誤字脱字がないか、必ず複数回チェックしましょう。
特に相手の名前や役職名、日付、場所などに間違いがないか、声に出して読み上げながら確認すると見落としを防げます。
文章の長さも重要です。
長すぎると読むのが大変になりますし、短すぎると気持ちが伝わりにくい場合があります。
関係性にもよりますが、一般的には数行から長くても便箋1枚程度に収まるようにまとめるのが良いでしょう。
伝えたいことがたくさんある場合は、簡潔にまとめて表現する工夫が必要です。
また、招待状の本文には書ききれない補足情報がある場合は、追伸(P.S.)を活用するのも一つの方法です。
例えば、二次会の案内や、当日の服装について触れたい場合など、本文とは直接関係ないけれど伝えておきたいことを追伸に書くことができます。
ただし、追伸に書く内容は、あくまでメインメッセージの補足に留め、重要な情報は本文に含めるようにしましょう。
句読点を使わない場合は、適切な場所でスペースを空け、文章の区切りが分かりやすいように配慮することも読みやすさにつながります。
返信はがきへの配慮も忘れずに
本人宛てメッセージは、招待状を受け取ったゲストへの心遣いですが、招待状全体の配慮として、返信はがきへの工夫も大切です。
返信はがきは、ゲストが出欠やアレルギーの有無などを新郎新婦に伝えるための重要なツールです。
ゲストが返信しやすいように、いくつかの点を考慮しましょう。
まず、返信期日を分かりやすく明記することは必須です。
期日を設けることで、ゲストはいつまでに返信すれば良いか明確に把握できます。
また、食物アレルギーの有無や、送迎バスの利用希望、宿泊の必要性など、ゲストが結婚式に安心して参加するための情報を提供してもらうための記入欄を設けると、ゲストへの配慮が伝わります。
これは、ゲストの安全や快適さに関わる重要な情報ですので、必ず確認できるようにしておきましょう。
さらに、返信はがきに「メッセージ記入欄」を設けることもおすすめです。
ゲストからお祝いのメッセージや、新郎新婦への質問などを自由に書いてもらえるスペースがあると、コミュニケーションが生まれます。
このメッセージ欄への記入は任意とすることで、ゲストに負担をかけすぎずに済みます。
ゲストへのメッセージだけでなく、ゲストが返信する際の負担を減らし、必要な情報をスムーズに集めるための配慮も、結婚式の準備を進める上で非常に重要です。
返信はがきも、ゲストへのおもてなしの一部として捉え、丁寧に準備を進めましょう。
まとめ
結婚式の招待状に添える本人宛てメッセージは、新郎新婦からゲストへの最初のおもてなしであり、お二人の温かい気持ちを伝えるための大切な手段です。
印刷された定型文だけでは伝わらない、一人ひとりに向けた感謝の気持ちや、これまでの思い出、結婚式への招待の想いをメッセージに込めることで、受け取ったゲストは深い喜びを感じ、結婚式への期待感を高めてくれるでしょう。
メッセージを書く際には、相手との関係性に応じて内容を書き分けることが重要です。
親しい友人には親しみやすく、目上の方には丁寧な言葉遣いで、兄弟姉妹にはこれまでの感謝を込めて、それぞれの関係性にふさわしい言葉を選びましょう。
忌み言葉や重ね言葉を避ける、句読点を使わないなどの基本的なマナーにも配慮することで、より丁寧で心のこもったメッセージになります。
メッセージ作成前にしっかりと準備をし、伝えたいエピソードを書き出しておくこと、そして誤字脱字がないか丁寧にチェックすることも忘れてはいけません。
また、返信はがきにアレルギー欄やメッセージ欄を設けるなど、ゲストが返信しやすいような配慮も大切です。
心を込めて書かれた本人宛てメッセージは、ゲストと新郎新婦の絆を深め、結婚式当日の感動へとつながる架け橋となるはずです。
ぜひこの記事を参考に、世界に一つだけの温かいメッセージを作成し、大切なゲストをお迎えください。