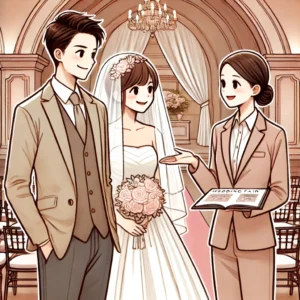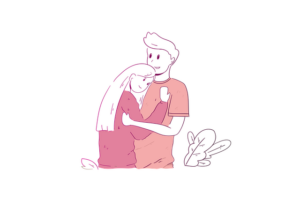結婚までにかかる費用はどれくらい?全体の目安と平均金額
結婚を考え始めたとき、多くの人が最初に気になるのが「結婚までにどれくらいお金がかかるのか」という点です。婚約から入籍、結婚式、新生活のスタートまで、必要な費用はさまざまです。平均的な金額を把握しておくことで、無理のない計画を立てることができます。
結婚にかかる費用は、選ぶスタイルや地域によって大きく異なりますが、一般的に「結婚資金」として用意される額は300万円〜500万円ほどが目安とされています。
これは婚約指輪や結婚式、新婚旅行、新生活の準備などを含んだ金額です。もちろん、これよりも少ない金額で結婚するカップルもいれば、1,000万円以上かけるケースもあります。
大きな支出となるのはやはり結婚式で、規模や演出によって大きく変動します。また、新居の準備や家具・家電の購入も負担になるため、結婚式だけではなく、その後の生活を見据えた計画が重要です。
では、具体的にどのくらいの金額が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
結婚資金はどのくらい必要?平均金額と最低額の目安
結婚資金の平均額は300万円〜500万円ですが、これはあくまで一般的な目安です。最低限必要な費用は、どのような形で結婚するかによって変わります。
例えば、結婚式を行わず、シンプルに入籍と新居の準備だけで済ませる場合、最低額は50万円〜100万円程度になることもあります。
これは婚姻届の提出費用、婚約指輪や結婚指輪の購入費、新生活のための引っ越し代や家具代などが含まれるためです。
一方で、結婚式を行う場合は、式の規模や内容によって金額が大きく異なります。国内での一般的な結婚式の費用は平均350万円前後と言われていますが、少人数の家族婚なら100万円以下でも可能ですし、大規模な披露宴を開けば500万円を超えることも珍しくありません。
また、新婚旅行の費用も考慮する必要があります。国内旅行なら20万円〜30万円、海外旅行なら50万円〜100万円以上になることもあり、行き先や宿泊先によって異なります。結婚資金を考える際には、「どこにお金をかけるのか」「どこを節約するのか」を明確にすることが大切です。
二人でいくら用意すべき?結婚準備の費用シミュレーション
実際に結婚するにあたって、「二人でどれくらいの貯金が必要なのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。理想的な結婚資金の貯め方を考えるために、以下のような費用シミュレーションをしてみます。
① 婚約・入籍にかかる費用
- 婚約指輪(20万円〜40万円)
- 結婚指輪(ペアで10万円〜30万円)
- 結婚届の提出費用(数千円程度)
② 結婚式・披露宴の費用
- 式場費用(100万円〜300万円)
- ドレス・タキシード(20万円〜50万円)
- 写真・映像撮影(10万円〜30万円)
- 料理・飲み物(50万円〜100万円)
③ 新生活の準備費用
- 引っ越し代(10万円〜30万円)
- 家具・家電(30万円〜100万円)
- 新居の初期費用(敷金・礼金などで50万円〜100万円)
こうした費用をすべて合わせると、一般的な結婚資金の総額は300万円〜500万円程度になります。
ただし、この金額をすべて自分たちで用意する必要はなく、親からの援助を受けるケースも少なくありません。両家からの支援額や、ご祝儀を活用することで、自己負担額を抑えることができます。
貯金なしでも結婚できる?費用を抑えるポイント
「貯金がないけど結婚したい」というカップルもいるでしょう。実際、貯金ゼロの状態でも結婚は可能ですが、いくつかの工夫が必要になります。
まず、費用を抑えるためには結婚式のスタイルを見直すことが重要です。例えば、家族だけの少人数婚にすれば、会場費や料理のコストを大幅に削減できます。フォトウェディング(写真撮影のみ)を選択することで、結婚式の費用を抑える方法もあります。
また、ご祝儀を活用することで、自己負担額を減らすことも可能です。結婚式を行う場合、ゲストからのご祝儀が収入源となります。
一般的に、ご祝儀総額は1人あたり3万円程度が相場となるため、50人のゲストを招待すれば約150万円の資金が得られる計算になります。これをうまく活用すれば、自己負担額を最小限に抑えた結婚が可能です。
さらに、新居の費用を抑えるためには、初期費用がかからない賃貸物件を選ぶ、家具や家電をレンタルする、リサイクル品を活用するといった方法もあります。
特に20代のカップルでは、これらの工夫をすることでスムーズに結婚生活をスタートさせることができるでしょう。
最後に、結婚資金をゼロから貯める場合には、結婚までの期間を1年〜2年設けるのも有効です。月々3万円ずつ貯金すれば、2年間で72万円、5万円ずつなら120万円貯まります。
結婚式を急がず、計画的に準備することで、無理のない結婚を実現できます。
結婚のどの段階でお金がかかる?費用の内訳を詳しく解説

結婚に向けた準備は段階的に進んでいきますが、その過程で必要な費用はさまざまです。婚約から入籍、結婚式、そして新生活のスタートまで、それぞれのタイミングでかかるお金を把握しておくことが大切です。
特に、結婚に関する費用は意外と見落としがちなものも多く、事前に計画を立てておくことで負担を軽減できます。
まず、婚約時には指輪の購入費用や結納・顔合わせの費用がかかります。その後、入籍のタイミングでは婚姻届の提出にかかる費用はわずかですが、引っ越しや新生活の準備を進めると大きな支出が発生します。
そして、結婚式や披露宴の費用は最も大きな割合を占めることが多く、平均的なカップルはここに数百万円単位の費用をかける傾向にあります。
さらに、新生活を始める際には、家具や家電の購入、引っ越し費用、家賃の初期費用などが必要となり、場合によっては結婚式以上のコストがかかることもあります。
では、それぞれの段階で具体的にどのような費用が必要になるのか、詳しく見ていきましょう。
婚約・入籍の費用は?指輪や結婚届のコスト
婚約時にかかる費用の中で最も大きなもののひとつが、婚約指輪の購入費用です。一般的な相場としては、20万円〜40万円程度が目安となっており、ブランドやデザインによって価格は大きく異なります。
最近では、シンプルなデザインで10万円前後の指輪を選ぶ人もいれば、50万円以上のハイブランドを購入する人もいるため、カップルの価値観に合わせた選択が重要です。
また、入籍前後には両家の顔合わせや結納が行われることが多く、これにも費用がかかります。顔合わせの食事会の費用は1人あたり1万円〜2万円が一般的で、両家6人で行えば合計6万円〜12万円程度がかかる計算になります。
結納を行う場合は、結納金として50万円〜100万円程度を準備するケースが多く、地域や家庭の習慣によって大きく異なります。
婚姻届の提出自体には役所の手続き費用はほぼかかりませんが、婚姻届のデザインにこだわったり、記念撮影をしたりするカップルも増えています。
さらに、結婚指輪(マリッジリング)の購入費用として、ペアで10万円〜30万円程度を想定しておくと良いでしょう。
結婚式・披露宴にかかる費用の相場と節約の工夫
結婚式・披露宴は、結婚における最も大きな支出のひとつです。全国平均では300万円〜400万円ほどかかるとされており、これは式場のレンタル費、料理、ドレス、装花、写真撮影など、さまざまな要素を含んでいます。
ゲストの人数や演出の内容によって金額は大きく変わり、少人数の家族婚なら100万円以下で収めることも可能ですし、豪華な演出を取り入れると500万円以上になることもあります。
節約の方法として、費用を抑えつつ理想の結婚式を実現するためには、優先順位を明確にすることが大切です。例えば、「料理にはこだわりたいが、装飾はシンプルでいい」「写真や動画はしっかり残したいが、演出は抑えめにする」など、自分たちにとって譲れないポイントを決めておくと、無駄な出費を抑えることができます。
また、オフシーズン(冬場や平日)に結婚式を行うと、式場のプランが割安になることが多いです。さらに、最近ではフォトウェディングのみを選択するカップルも増えており、これなら10万円〜30万円程度で結婚の記念を残すことができます。
ゲストからのご祝儀を考慮すると、自己負担額を大幅に軽減できる場合もあります。一般的に、1人あたりのご祝儀相場は3万円程度なので、50人招待すれば約150万円のご祝儀収入が得られる計算になります。
この金額を式の費用に充てることで、自己負担を減らすことが可能です。
新生活の準備費用は?家具・家電・引っ越し費用をチェック
結婚式の準備と並行して、新生活のための費用も考えておく必要があります。新居を決める際には、家賃だけでなく、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用がかかる点に注意が必要です。
一般的に、新居の初期費用は家賃の4〜6か月分がかかるため、家賃10万円の物件に住む場合は40万円〜60万円を見込んでおくと安心です。
また、引っ越し費用も忘れてはいけません。引っ越し代の相場は単身で3万円〜10万円、二人暮らしなら10万円〜20万円程度になります。
繁忙期(3月〜4月)は料金が高騰するため、費用を抑えるならオフシーズンの引っ越しを検討するとよいでしょう。
さらに、家具や家電の購入費用も必要です。必要最低限のものをそろえるだけでも、冷蔵庫・洗濯機・テレビ・ベッド・ダイニングテーブルなどで30万円〜50万円はかかるでしょう。
新婚生活をスムーズにスタートさせるためには、あらかじめ必要なものをリストアップし、予算を確保しておくことが重要です。
費用を抑える方法としては、中古家具や家電を活用する、リサイクルショップやフリマアプリを利用する、レンタルサービスを活用するといった手段もあります。
最近では、サブスクリプション型の家具・家電レンタルも人気があり、初期費用を抑えながら新生活を始めることができます。
20代・30代の結婚資金の貯め方と計画的な準備

結婚を考え始めたとき、最初に気になるのが「結婚資金をどう準備するか」です。特に20代・30代は、まだ貯金が十分にない場合も多く、どれくらいの費用が必要なのか、どうやって貯めればいいのかを具体的に知りたい人も多いでしょう。
結婚には、婚約指輪や結婚式、新居の準備など、多くの費用がかかります。計画的に貯金を進めることで、無理なく理想の結婚を実現することができます。
20代と30代では、収入やライフスタイルが異なるため、貯金の仕方も変わってきます。20代はまだ収入が少ないものの、早めに計画を立てることで将来の負担を減らせます。
一方、30代では貯金額がある程度増えていることが多く、具体的な目標を持ちやすくなります。どのように結婚資金を貯めるべきか、詳しく見ていきましょう。
20代・30代でどのくらい貯金すれば安心?目安を紹介
結婚資金の目安は、結婚式のスタイルや新生活の準備にどれくらいお金をかけるかによって変わりますが、一般的には二人で300万円〜500万円程度を準備するケースが多いです。
20代の場合、まだ貯金額が少ないこともありますが、毎月1万円〜3万円を積み立てるだけでも、数年後には大きな資金になります。
例えば、25歳から2年間、毎月3万円ずつ貯めれば72万円、ボーナスから10万円ずつ追加すれば、100万円を超える貯金が可能です。
30代になると、収入が増え貯金のペースを上げることができるため、目標額を具体的に設定しやすくなります。結婚式だけでなく、新居の準備や新婚旅行の費用も考慮すると、30代で貯めておきたい目安としては200万円〜300万円程度が理想です。
また、結婚費用はすべて自分たちで用意する必要はありません。親からの援助や、ご祝儀を活用することで、実際に自己負担する金額を減らすことも可能です。
どれくらい貯めるべきか迷ったら、まずは結婚にかかる費用のシミュレーションをし、二人で話し合って計画を立てるのがおすすめです。
男性・女性で違う?結婚費用の分担と現実的な予算設定
結婚資金の負担割合は、カップルによって異なりますが、一般的には男性の方が多めに負担する傾向にあります。これは、婚約指輪や結婚式の費用を男性側が多めに支払うケースが多いためです。
しかし、最近では共働きが一般的になり、「二人で協力して費用を分担する」という考え方も増えています。
例えば、婚約指輪や結婚式の費用は男性が多めに負担し、新居の初期費用や家具・家電の購入は女性が多めに出すといった分担方法もあります。
「結婚式は男性7割・女性3割、新生活の費用は半々」といった割合が一般的ですが、カップルごとに話し合い、納得のいく形で分担することが大切です。
また、「結婚費用は親に頼りたくない」というカップルもいるでしょう。その場合は、無理のない範囲でお互いがどれくらい貯めるのかを決めておくのがおすすめです。
お互いの収入や貯金額に合わせて、無理なく支払える方法を考えることで、結婚後の生活にも余裕が生まれます。
無理なく貯める方法とは?賢い貯金術と支援制度の活用
結婚資金を貯めるためには、無理のない貯金計画を立てることが重要です。特に20代のうちは、生活費や趣味にもお金を使いたい時期ですが、少しずつでも積み立てることで、後々の負担が軽くなります。
まず、毎月の収入の中から自動的に一定額を積み立てる「先取り貯金」をすると、無駄遣いを防ぎながら貯金ができます。
例えば、給料日に5万円を貯金用口座に移し、残ったお金で生活する方法を取り入れると、着実に資金を増やすことが可能です。
また、結婚資金を貯める際には、ボーナスの活用も効果的です。ボーナスのうち10万円〜20万円を結婚資金として確保すれば、1年で大きな貯金ができます。
さらに、副業を活用して収入を増やすのも一つの方法です。最近では、スキマ時間でできる副業が増えており、数万円の追加収入を得ることができます。
また、自治体の支援制度を活用するのもおすすめです。地域によっては、「結婚新生活支援補助金」といった制度があり、新居の家賃や引っ越し費用の一部を補助してくれる自治体もあります。
例えば、特定の市区町村では、新婚夫婦に対して最大30万円の補助を行っているケースもあるため、自分たちの住む地域の制度を調べてみるとよいでしょう。
さらに、クレジットカードのポイントやマイルを活用して、新婚旅行や家具購入の費用を抑える方法もあります。普段の買い物で貯めたポイントを結婚関連の支払いに充てることで、出費を軽減できます。
結婚までにかかる費用はいくら?20代・30代の貯金計画と節約のコツのまとめ
結婚資金を貯めるには、20代・30代のライフスタイルに合わせた計画が重要です。20代は少額からコツコツ積み立てることが大切であり、30代は具体的な目標額を設定して効率的に貯めるのがおすすめです。
結婚費用の分担については、男性・女性での負担割合を話し合い、お互いに納得できる形で計画を立てることが大切です。
また、無理なく貯めるためには、先取り貯金やボーナスの活用、自治体の支援制度を活用するといった工夫が有効です。
結婚は人生の大きなイベントだからこそ、無理のない範囲で資金を準備し、理想の結婚を叶えましょう。